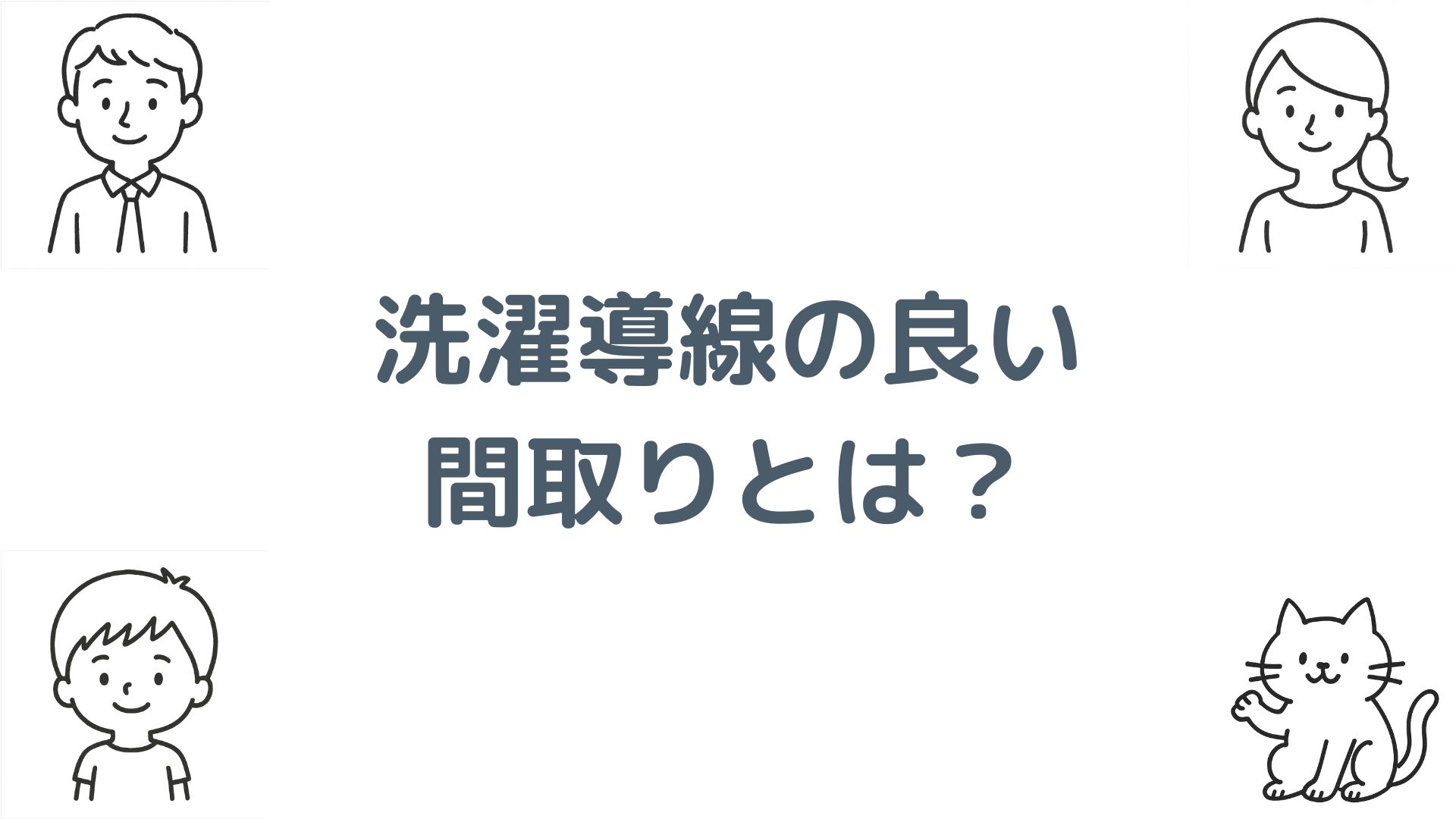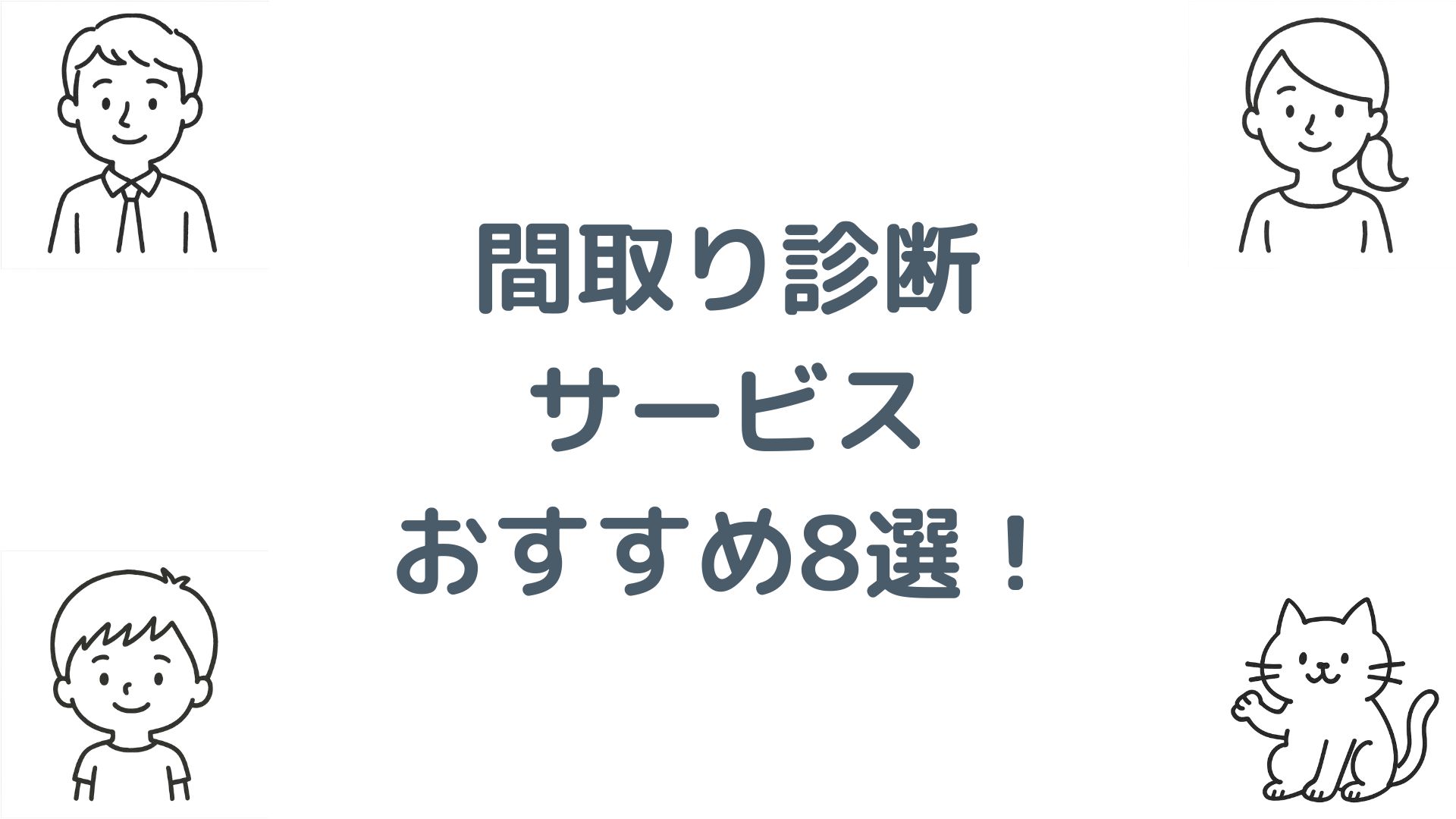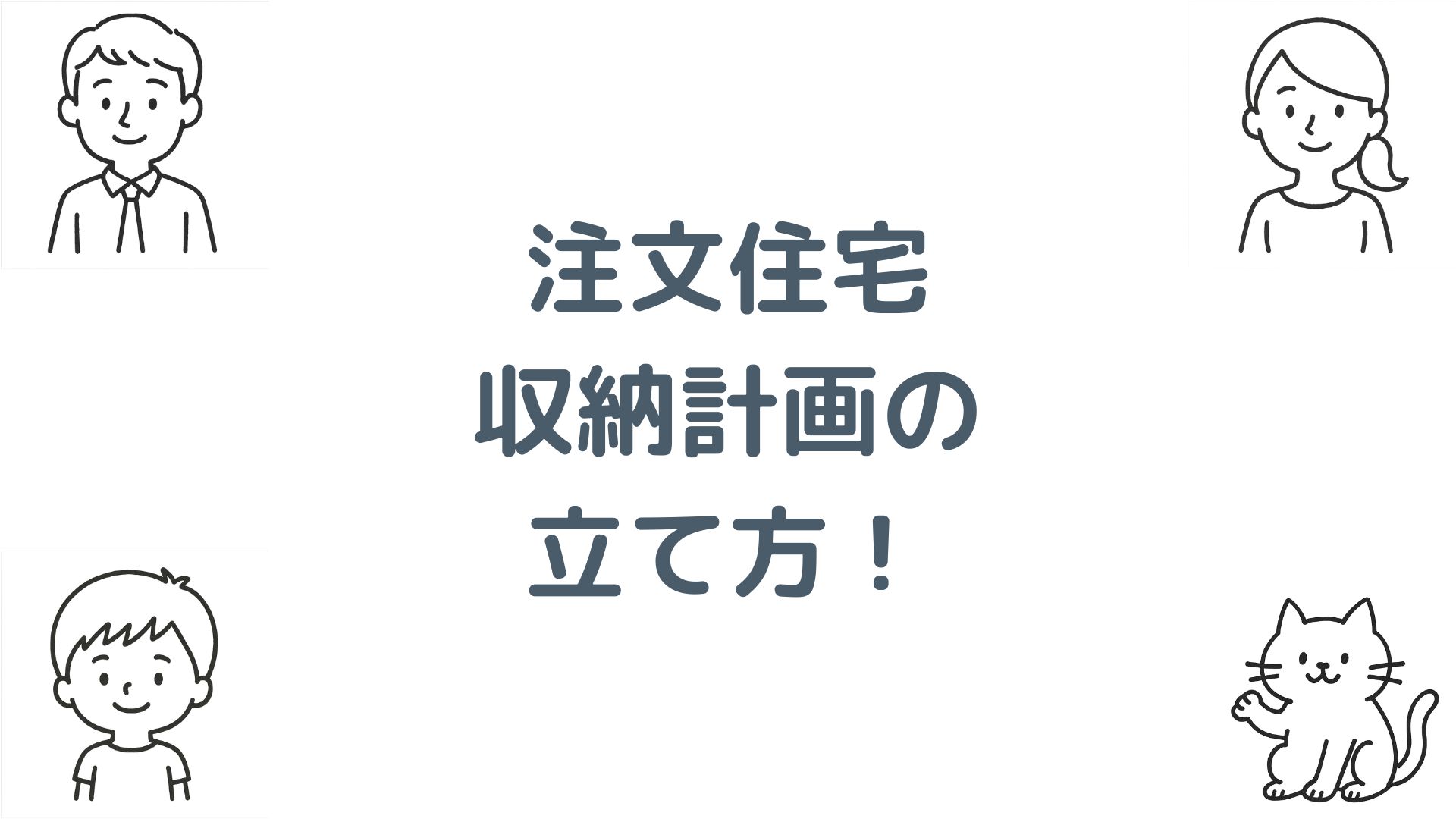こんな方におすすめ
今回は、間取りで後悔だらけについて解説していきます。
家づくりを進めながら、
「この間取りで本当に後悔しないかな…」
「失敗したら取り返しがつかないし、どう判断すればいいのかわからない…」
と不安になりますよね。
実際、注文住宅では“間取りの失敗”が最も多く、「間取りで後悔だらけになった」という声は珍しくありません。
ARINA株式会社の調査でも、新築で後悔したことの第1位は間取りでした。
図面では完璧に見えても、住み始めてから「動線が使いにくい」「収納が足りなくて困る」「こんなはずじゃなかった…」と気づくケースは非常に多いもの。
しかし、こうした後悔には必ず理由があり、事前に知っておけばほとんどの失敗は回避できます。
この記事では、玄関・リビング・キッチンの場所別の後悔から、動線・収納・設備といった要素別の落とし穴まで、「間取りで後悔だらけ」になりやすいポイントを具体例と対策付きで徹底解説します。
最後まで読めば、間取りの迷いが消え、あなたが“後悔しない家づくり”を自信を持って進められるようになりますよ。
目次
- 間取りで後悔だらけになりがちな場所別の失敗例
- 間取りで後悔だらけになりがちな機能・要素別の見落としポイント
- 間取りで後悔だらけ!実は導入して要らなかった設備ワースト7
- 間取りで後悔だらけにならないための鉄則5つ
- 間取りで後悔だらけに関するQ&A
- Q1. いま出てる間取り案って、本当に暮らしやすいの?後から「やっぱ失敗した」ってならない?
- Q2. 家づくり初心者でも、間取りの良し悪しが見抜けるチェックポイントってある?
- Q3. 間取りを何回修正しても不安…これ以上直す必要ないラインってどこ?
- Q4. 間取りで後悔だらけにならないために、最低限やっといた方がいい優先順位って?
- Q5. 家族と意見が合わなくて間取りが進まない…どうすれば決めやすくなる?
- Q6. モデルハウスって何を見ればいい?広すぎて参考にならないんだけど…
- Q7. 収納は多ければ安心って思ってるけど、実際どうなの?
- Q8. コンセントやスイッチってどのくらい細かく決めておくべき?後悔しやすい?
- Q9. 自分で考えた間取りが正しいか、第三者にチェックしてもらう方法ってある?
- Q10. 今の家が住みにくいのは分かってるけど、どう言語化すれば間取りに反映できる?
- Q11. 家って何歳から買うのがベスト?逆に買っちゃダメな年齢とかある?
- Q12. 1000万円以下で家を建てるって実際どう?ローコスト住宅って大丈夫?
- Q13. やばい家って具体的にどんな特徴があるの?買ったら後悔するやつ?
- Q14. 買ってはいけない一戸建ての条件ってある?見極めポイント知りたい
- Q15. 間取りで後悔しすぎて立ち直れない…どうやって気持ち切り替えればいい?
- Q16. オーバーハングの家って実際どう?後悔するって聞くけど本当?
- Q17. 庭のない家って住んでみてどう?後悔する人多い?
- Q18. マイホーム買ってから後悔しすぎて鬱っぽい…どうすればいい?
- 間取りで後悔だらけまとめ
間取りで後悔だらけになりがちな場所別の失敗例
まずは、玄関やリビングといった特定の空間ごとに、よくある失敗例とその原因、対策を見ていきましょう。
【玄関】家の顔でつまずく後悔5選
毎日必ず通り、お客様を最初にお迎えする玄関。ここでの失敗は、日々の小さなストレスや家の第一印象に直結します。
① 収納が絶望的に足りない
最も多い後悔が収納不足。
靴はもちろん、傘、ベビーカー、子どもの外遊び用おもちゃ、アウトドア用品、コート類など、玄関周りで収納したいものは意外と多いもの。
これらを収納するスペース、特に土間収納が不足すると、玄関が常に物で溢れかえり、散らかった印象を与えてしまいます。
② 玄関ドアを開けたら、中が丸見え
玄関ドアを開けた正面にトイレや洗面所・脱衣所のドアがあると、来客時に家族が使いにくかったり、生活感が見えてしまったりして気まずい思いをします。
また、道路から玄関ドアが直接見える間取りだと、出入りの際に通行人と目が合ってしまうなど、プライバシーの観点からも問題です。
③ とにかく狭くて暗い
図面では十分だと思っても、実際に家族が並んで靴を履いたり、大きな荷物を持っていたりすると窮屈に感じるケースは少なくありません。
また、採光窓がなかったり、位置が悪かったりすると、日中でも薄暗く、じめっとした印象の玄関になってしまいます。
④ 2Way玄関がただの遠回りに
来客用と家族用で動線を分ける2Way玄関は人気ですが、設計が悪いと、ただ遠回りになるだけの「回遊することが目的の動線」になってしまいます。
結局、便利な来客用ばかりを家族が使ってしまい、家族用玄関がただの物置になるという本末転倒な結果にもなりかねません。
⑤ 設備・仕様の選択ミス
「照明を人感センサーにしておけばよかった」「荷物で両手がふさがっている時にスマートキーが便利だった」といった設備面での後悔や、「汚れが目立ちにくいタイルにすればよかった」といった仕様面での後悔もよく聞かれます。
【リビング】家族団らんの中心地での後悔5選
家の中で最も長く過ごすリビング。だからこそ、ここでの後悔は住み心地に大きく影響します。
① 広すぎた、もしくは狭すぎた
「LDKは20畳以上」といった憧れだけで広さを決めると、実際に家具を置いてみたらスカスカで落ち着かなかったり、冷暖房の効率が悪く光熱費がかさんだりすることがあります。
逆に、図面上の数字だけを見て「これで十分」と判断すると、ソファやダイニングテーブルを置いた後に人が通るスペースがギリギリになってしまうことも。
② リビング階段・吹き抜けの罠
開放感があり、家族の気配を感じられると人気のリビング階段や吹き抜け。
しかし、断熱・気密性能が低い家では、冬は暖かい空気がすべて2階へ逃げて1階が極寒に、夏は2階が灼熱地獄になるという大きな欠点があります。
また、音や匂いが家中に伝わりやすいというデメリットも。
③ 窓の配置が大失敗
「南向きで日当たりが良いはずが、テレビに光が反射して画面が見えない」「大きな窓を付けたはいいが、隣家や道路からの視線が気になって結局カーテンを閉めっぱなし」といった窓に関する後悔は後を絶ちません。
ソファの真後ろに窓があると、落ち着かないだけでなく、庭の景色を楽しめないという残念な配置になることもあります。
④ 収納がなくて物が溢れる
リビングは、リモコンやティッシュ、雑誌、子どものおもちゃ、書類など、細々とした生活用品が集まる場所。
これらをしまうための収納を計画していないと、テーブルの上が常に散らかった状態になってしまいます。
⑤ 生活音が筒抜けで落ち着かない
リビングのすぐ隣に寝室や書斎を配置してしまうと、家族がテレビを見ている音で眠れなかったり、仕事に集中できなかったりします。
トイレが近い場合も、来客中にお互いが音を気にしてしまうなど、ストレスの原因になります。
【キッチン&ダイニング】毎日の家事を左右する後悔5選
食事の準備から片付けまで、毎日何度も使うキッチンとダイニング。ここの使い勝手が、日々の家事ストレスを大きく左右します。
① 通路幅が狭くてすれ違えない
キッチンの通路幅は非常に重要です。一人で作業するのか、夫婦二人で立つことが多いのかによって必要な幅は変わります。
冷蔵庫や食洗機のドアを開けた状態でも人が通れるか、といった点も見落としがちです。
② 冷蔵庫の位置が最悪
「キッチンの奥に冷蔵庫を置いたら、料理中に家族が飲み物を取りに来るたびに動線を塞がれる」「リビングから冷蔵庫の側面が丸見えで生活感が出てしまう」といった後悔も多いです。
③ ゴミ箱の置き場所がない
設計段階で意外と忘れがちなのがゴミ箱のスペース。
分別用に複数置くことを想定しておらず、結局通路にはみ出して邪魔になったり、見た目を損ねたりするケースがよくあります。
④ ダイニングが狭くて椅子が引けない
置きたいダイニングテーブルのサイズだけでなく、椅子を引いて人が座ったり、テーブルの後ろを通ったりするスペースまで考えていないと、非常に窮屈な空間になってしまいます。
⑤ ペンダントライトの位置を動かせない
ダイニングテーブルの上に吊るすペンダントライトはおしゃれですが、一度設置すると位置を動かせません。
テーブルのサイズを変えたり、レイアウトを変更したりした際に、照明がテーブルの中心からずれてしまうことがあります。
間取りで後悔だらけになりがちな機能・要素別の見落としポイント
特定の部屋だけでなく、家全体の機能性に関わる要素での失敗も多く見られます。
【動線計画】回遊の罠と分断の悲劇
洗濯動線が最悪
「1階の洗面所で洗濯し、2階のベランダに干し、乾いたら1階のリビングで畳んで、各階のクローゼットにしまう」…このような分断された洗濯動線は、毎日の家事を苦行に変えます。「洗う→干す→畳む→しまう」という一連の作業がスムーズに行えるかが鍵です。
来客動線がプライベートと交錯
玄関からリビングへお客様を案内する途中に、洗面所や寝室などプライベートな空間が丸見えになってしまう間取りは避けたいところです。
ただ回れるだけの回遊動線: 回遊動線は便利ですが、目的なく設けるとただ通路が増えるだけで、部屋や収納が狭くなる原因になります。
【収納計画】量より質と場所
適材適所にない収納
たとえ大きな納戸があっても、使う場所から遠ければ意味がありません。
掃除機はリビングの近くに、トイレットペーパーのストックはトイレの近くに、というように「使う場所にしまう」のが鉄則です。
ウォークインクローゼット幻想
憧れのウォークインクローゼット(WIC)ですが、通路部分が必要なため、同じ面積の壁面クローゼットに比べて収納効率が落ちることがあります。
奥行きが深すぎる収納の使いにくさ: 奥行きのある押し入れタイプの収納は、奥に入れたものがデッドストック化しがちです。
何を収納するかに合わせて適切な奥行きを考える必要があります。
【コンセント・スイッチ・照明】暮らし始めて気づく不便
コンセントが足りない・位置が悪い
「掃除機をかけるたびに延長コードが必要」「ベッドサイドでスマホを充電できない」「家具を置いたらコンセントが隠れた」などは、定番の後悔ポイントです。
スイッチが動線の先じゃない
部屋に入ってから壁伝いに歩いた先にスイッチがあると、暗い中で手探りすることになり不便です。
ダウンライトだらけで眩しい
近年の住宅で多用されるダウンライトですが、安易に並べすぎると天井がごちゃごちゃして見えたり、ソファに座った時に光源が直接目に入って眩しく感じたりすることがあります。
間取りで後悔だらけ!実は導入して要らなかった設備ワースト7
憧れて採用したものの、「思ったより使わなかった」「メンテナンスが大変」という声が多い設備もあります。
本当に必要か、ライフスタイルに合っているか、慎重に検討しましょう。
ベランダ・バルコニー
洗濯物を干す場所として設置したものの、共働きで室内干しがメインだったり、花粉やPM2.5が気になって外に干さなかったりして、結局使わなくなるケースが多いです。
定期的な防水メンテナンスにもコストがかかります。
勝手口
ゴミ出しなどに便利と思いきや、すぐ近くに玄関や掃き出し窓があれば代用できることも。
断熱性の低下や防犯面でのリスク、コストアップにつながるため、本当に必要か検討が必要です。
浴室乾燥機
雨の日の洗濯に便利ですが、電気代が高く、乾燥に時間がかかるのがネック。 高性能な除湿機やドラム式洗濯乾燥機で十分代用できる場合も多いです。
食洗機(特に浅型)
手間が省けると人気の食洗機ですが、予洗いが面倒だったり、思ったより食器が入らなかったり(特に浅型)、大きな鍋やフライパンは結局手洗いになったりして、使わなくなってしまう人もいます。
客間としての和室
「お客様が泊まりに来た時のために」と設けた和室が、年に数回しか使われず、普段は物置になっている…というは非常によくある話です。
ロフト
子どもの遊び場や収納スペースとして人気ですが、夏場は熱気がこもって非常に暑く、ハシゴの上り下りが面倒で、結局「開かずの間」になりがちです。
浴室の窓
換気や採光目的で設置しても、実際は換気扇で十分だったり、防犯面やプライバシーが気になって開けられなかったりすることが多い設備。
掃除の手間が増えるというデメリットもあります。
間取りで後悔だらけにならないための鉄則5つ
これまで見てきた数々の失敗例。これらを回避し、理想の家づくりを成功させるためには、計画段階で踏むべき重要なステップがあります。
鉄則1:現状の不満と理想の暮らしを徹底的に言語化する
新しい家の間取りを考える前に、まずは今住んでいる家の「良い点」と「不満な点」を家族全員で書き出しましょう。
そして、「新しい家でどんな暮らしがしたいか」「どんな時間を大切にしたいか」を具体的に話し合います。
- 「朝は光を浴びながらコーヒーを飲みたい」
- 「休日は家族で庭でBBQがしたい」
- 「洗濯は週末にまとめて一気に片付けたい」
…こうした具体的なシーンを想像することが、間取りの骨格になります。
これらを「家づくりノート」にまとめ、譲れない要望に優先順位をつけておきましょう。
鉄則2:情報収集とリアルな体感を怠らない
SNSや住宅情報サイト、ハウスメーカーのカタログを見てイメージを膨らませることは大切です。
しかし、図面や写真だけでは、空間の広さや天井の高さ、素材の質感といった「スケール感」は決してわかりません。
必ずモデルハウスや完成見学会に足を運び、実際にその空間を歩き、広さを体感してください。
メジャーを持参して、通路幅や天井高を測ってみるのも良いでしょう。この「リアルな体感」の積み重ねが、図面と現実のギャップを埋めてくれます。
鉄則3:1社の提案を鵜呑みにせず必ず複数のプランを比較する
家づくりは、パートナーとなる住宅会社選びが非常に重要です。そして、間取りの提案は、設計士の経験やセンスによって大きく変わります。
最初から1社に絞り込まず、複数の会社に同じ要望を伝えて、間取りプランを提案してもらいましょう。
A社では実現不可能と言われたことが、B社のアイデアで解決することもあります。
それぞれのプランの良いところを組み合わせることで、より理想に近い間取りにたどり着くことができます。
鉄則4:図面上で仮想生活シミュレーションを繰り返す
間取りプランがある程度固まったら、その図面の上で、とことん生活をシミュレーションします。
- 家具を書き込む: 今使っている家具や、新しく購入予定の家具のサイズを正確に測り、図面に書き込みます。
- 動線を書き込む: 朝起きてから、顔を洗い、着替え、朝食をとり、出かけるまで…といった一連の動きを線でなぞってみます。
- ドアの開閉を描く: 部屋のドアや収納の扉を開けた時、人にぶつかったり、通路を塞いだりしないか確認します。
この地道な作業が、住み始めてからの「こんなはずじゃなかった」を防ぐ最も有効な手段です。
鉄則5:プロを信頼し任せる勇気も持つ
施主の要望をすべて盛り込もうとすると、動線が複雑になったり、ちぐはぐな空間になったりすることがあります。
家づくりのプロである設計士は、数多くの経験から、より良い解決策を知っているはずです。
自分たちの要望をしっかりと伝えた上で、プロからの提案にも耳を傾ける柔軟性を持ちましょう。
時には、こだわりを少し手放し、「プロにお任せする」という勇気を持つことも、結果としてバランスの取れた良い家につながることがあります。
間取りで後悔だらけに関するQ&A
間取りで後悔だらけに関するQ&Aに回答していきます。
Q1. いま出てる間取り案って、本当に暮らしやすいの?後から「やっぱ失敗した」ってならない?
A1. 間取りの良し悪しは、図面だけでは判断が難しいため「生活動線」「家具配置」「窓の光の入り方」の3点を必ずシミュレーションすることが大切です。
朝〜夜までの行動を書き出し、家具サイズを書き込むだけでも失敗リスクは大幅に下がります。モデルハウスで広さを体感することもおすすめです。
Q2. 家づくり初心者でも、間取りの良し悪しが見抜けるチェックポイントってある?
A2. 初心者でも判断できるポイントは「動線の長さ」「収納の位置」「光と視線の入り方」の3つです。
特に“使う場所の近くに収納があるか”と“来客時に生活感が丸見えにならないか”は後悔しやすい部分なので、図面上で必ず確認することをおすすめします。
Q3. 間取りを何回修正しても不安…これ以上直す必要ないラインってどこ?
A3. 修正の目安は「家事がスムーズになるか」「家族が快適に過ごせるか」「プロが懸念を示していないか」の3つです。
逆に細部のこだわりすぎは全体のバランスを崩す原因にもなります。第三者のプロ(別会社含む)の意見を一度入れると判断しやすくなります。
Q4. 間取りで後悔だらけにならないために、最低限やっといた方がいい優先順位って?
A4. 優先すべきは「①動線」「②収納の場所」「③採光と視線」「④性能(断熱・気密)」「⑤将来の変化」の順番です。
おしゃれさは後回しでも問題ありませんが、この5つは改善の難易度が高いため、最初にしっかり固めておく必要があります。
Q5. 家族と意見が合わなくて間取りが進まない…どうすれば決めやすくなる?
A5. まず「現状の不満」と「理想の暮らし」を家族ごとに書き出し、優先順位を可視化するのがおすすめです。
共通点や外せない条件が浮き彫りになるため、対立が減ります。家づくりノートで要望を整理すると、設計士にも伝わりやすくなります。
Q6. モデルハウスって何を見ればいい?広すぎて参考にならないんだけど…
A6. 見るべきは「通路幅」「玄関や収納の使い勝手」「窓と光の入り方」「音の響き方」です。
高級仕様は真似できなくても“広さの体感”だけは絶対に得られます。
メジャーを持って行き、気になった距離はその場で測ると家づくり精度が上がります。
Q7. 収納は多ければ安心って思ってるけど、実際どうなの?
A7. 「量」より「場所」の方が圧倒的に重要です。家中の持ち物をリストにして“使う場所の近くに収納する”を徹底すると無駄がなくなります。
大きい納戸より、必要な位置に小さな収納を散らす方が日々のストレスは軽減されます。
Q8. コンセントやスイッチってどのくらい細かく決めておくべき?後悔しやすい?
A8. コンセント・スイッチは「家具配置を決めてから」が鉄則です。
掃除機やスマホ充電のように頻度の高い家電をどこで使うかを図面上で書き込むと必要な数が見えてきます。
暮らし始めてからの後悔が多い部分なので、早めに計画すると安心です。
Q9. 自分で考えた間取りが正しいか、第三者にチェックしてもらう方法ってある?
A9. ハウスメーカー以外の“外部の設計士”や“間取り診断サービス”を利用する方法があります。
プロは視線・音・光・動線の矛盾を見抜くため、施主が気づかない欠点を指摘してくれます。複数社の提案を比較するだけでも精度が劇的に上がります。
Q10. 今の家が住みにくいのは分かってるけど、どう言語化すれば間取りに反映できる?
A10. 現在の家で困っていることを「場所・状況・行動」の3つに分解すると言語化しやすくなります。
例えば「玄関が狭い→朝の登校時間に渋滞→靴が散乱」という具合です。この“具体的な困りごと”が、理想の間取りを作る最も実用的な材料になります。
Q11. 家って何歳から買うのがベスト?逆に買っちゃダメな年齢とかある?
A11. 明確に「買ってはいけない年齢」はありませんが、住宅ローンは返済期間が長いため“完済年齢”が重要になります。
一般的には、60〜65歳までに完済できる計画が理想です。
40代以降でも、頭金を増やす・返済期間を短くする・繰上げ返済を計画すると安心して購入できます。
Q12. 1000万円以下で家を建てるって実際どう?ローコスト住宅って大丈夫?
A12. 1000万円以下の住宅は「間取りのシンプル化」「標準仕様の固定化」でコストを抑えています。
基本性能(耐震・断熱)が法基準を満たしていれば問題ありませんが、設備の自由度が低い点やメンテナンス費が将来かかる可能性を理解した上で選ぶと後悔しにくいです。
Q13. やばい家って具体的にどんな特徴があるの?買ったら後悔するやつ?
A13. 多いのは「日当たりが悪い」「立地が悪い(騒音・坂がきつい)」「隣家との距離が近すぎる」「動線が破綻してる」「収納が圧倒的に少ない」などです。
これらは後から改善が難しいため、物件を見る際は“直せない部分”を最優先でチェックするのがおすすめです。
Q14. 買ってはいけない一戸建ての条件ってある?見極めポイント知りたい
A14. 注意すべきは「道路が狭い」「浸水ハザードが高い」「地盤の調査書がない」「違法増築の可能性」「再建築不可」などです。
間取りや設備は後から直せても、立地・地盤・法的要件は変更できません。不動産会社任せにせず、自治体のハザードマップも必ず確認しましょう。
Q15. 間取りで後悔しすぎて立ち直れない…どうやって気持ち切り替えればいい?
A15. 後悔ポイントが明確なら「改善できる部分」と「変更が難しい部分」に分けて整理すると前に進みやすくなります。
家具の配置や収納改善で解消できることも多く、リフォームで動線を整える方法もあります。
大切なのは「失敗=終わり」ではなく、後から十分調整できる点を知ることです。
Q16. オーバーハングの家って実際どう?後悔するって聞くけど本当?
A16. オーバーハングはデザイン性が高いですが、「構造計算が複雑」「建築コストが上がりやすい」「外壁や雨仕舞のメンテ費が高くなる」などのデメリットがあります。
設計力の高い会社なら問題ありませんが、コスト重視で採用すると後悔するパターンが多いため慎重に検討するのがおすすめです。
Q17. 庭のない家って住んでみてどう?後悔する人多い?
A17. 庭なし住宅は「管理が楽」「駐車場を広く取れる」などのメリットがありますが、「子どもの遊び場がない」「BBQや家庭菜園ができない」「洗濯が干しにくい」など生活の幅が制限されるケースもあります。
外遊びを重視する家庭は後から後悔しやすい傾向があります。
Q18. マイホーム買ってから後悔しすぎて鬱っぽい…どうすればいい?
A18. マイホームブルーは多くの人が経験します。
まずは「後悔ポイントの原因」を紙に書き出し、“改善可能な部分”から一つずつ整えていくことで、気持ちの重さが軽減します。
リフォームや家具配置の見直しで劇的に改善する例もあり、自治体の無料相談窓口や専門家に相談するのも有効です。
間取りで後悔だらけまとめ
今回は、間取りで後悔だらけについて解説しました。
注文住宅の間取りづくりは、まさに十人十色。正解がないからこそ、悩み、迷うのは当然のことです。
しかし、多くの人が陥る「後悔だらけ」のパターンには、共通点があることも事実。
今回ご紹介した数々の失敗例は、いわば家づくりの「転ばぬ先の杖」です。
これらの知識を武器に、家族の理想の暮らしを具体的に描き、プロの力も借りながら、徹底的にシミュレーションを重ねる。
このプロセスを丁寧に進めることこそが、後悔のない家づくりへの唯一の道です。
大変な道のりではありますが、この記事が、あなたの「後悔だらけの家」を「一生愛せる最高の我が家」に変える一助となれば、これほど嬉しいことはありません。
洗濯導線の良い間取りとは?家事負担を減らすランドリールーム・収納・動線設計を徹底解説!
-

-
洗濯導線の良い間取りとは?家事負担を減らすランドリールーム・収納・動線設計を徹底解説!
続きを見る
間取り診断サービスおすすめ8選を紹介!セカンドオピニオンの選び方と費用相場は?
-

-
間取り診断サービスおすすめ8選を紹介!セカンドオピニオンの選び方と費用相場は?
続きを見る
注文住宅の収納計画の立て方!後悔しない間取りを実現する4つのステップと場所別アイデアを解説!
-

-
注文住宅の収納計画の立て方!後悔しない間取りを実現する4つのステップと場所別アイデアを解説!
続きを見る