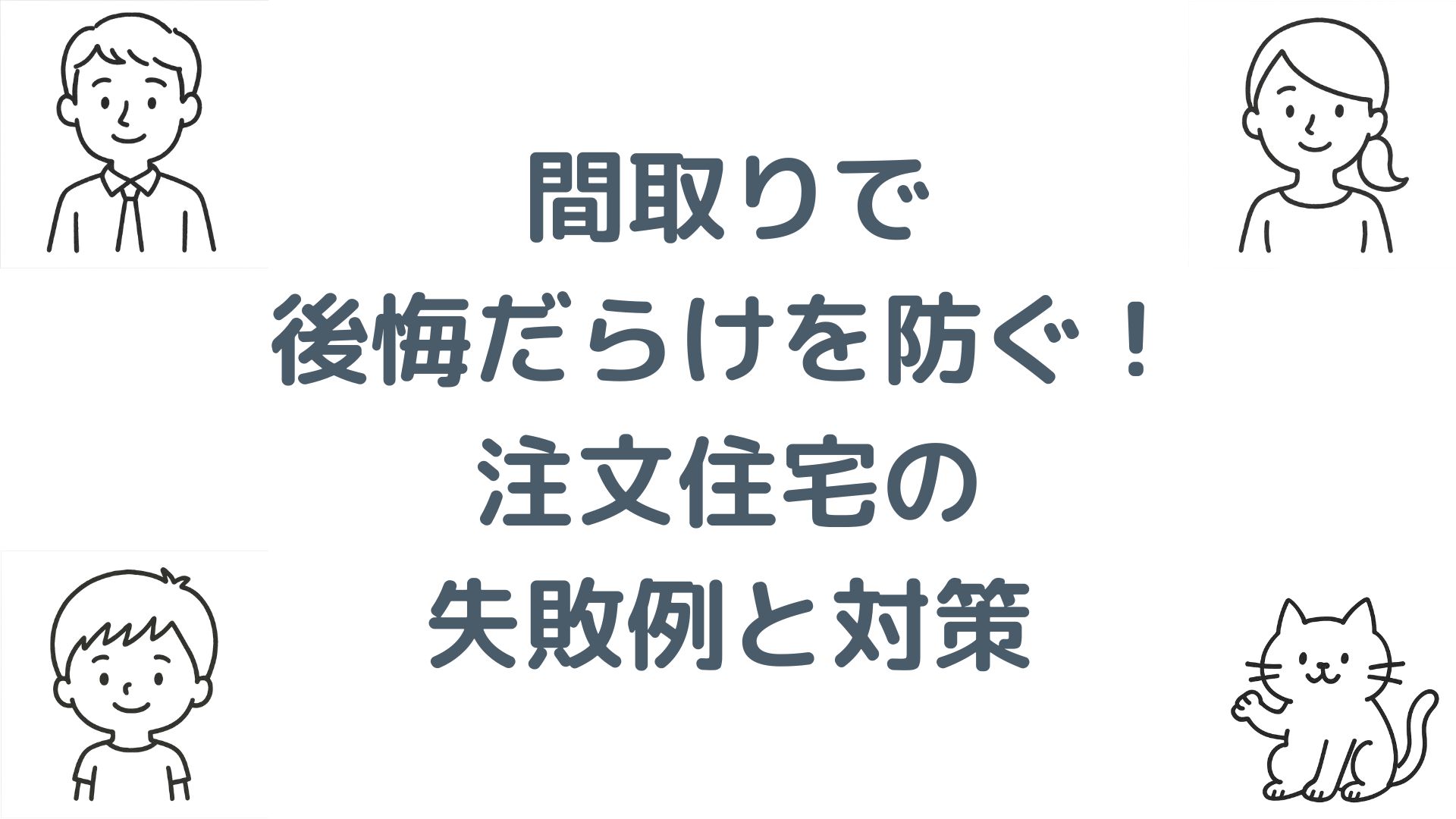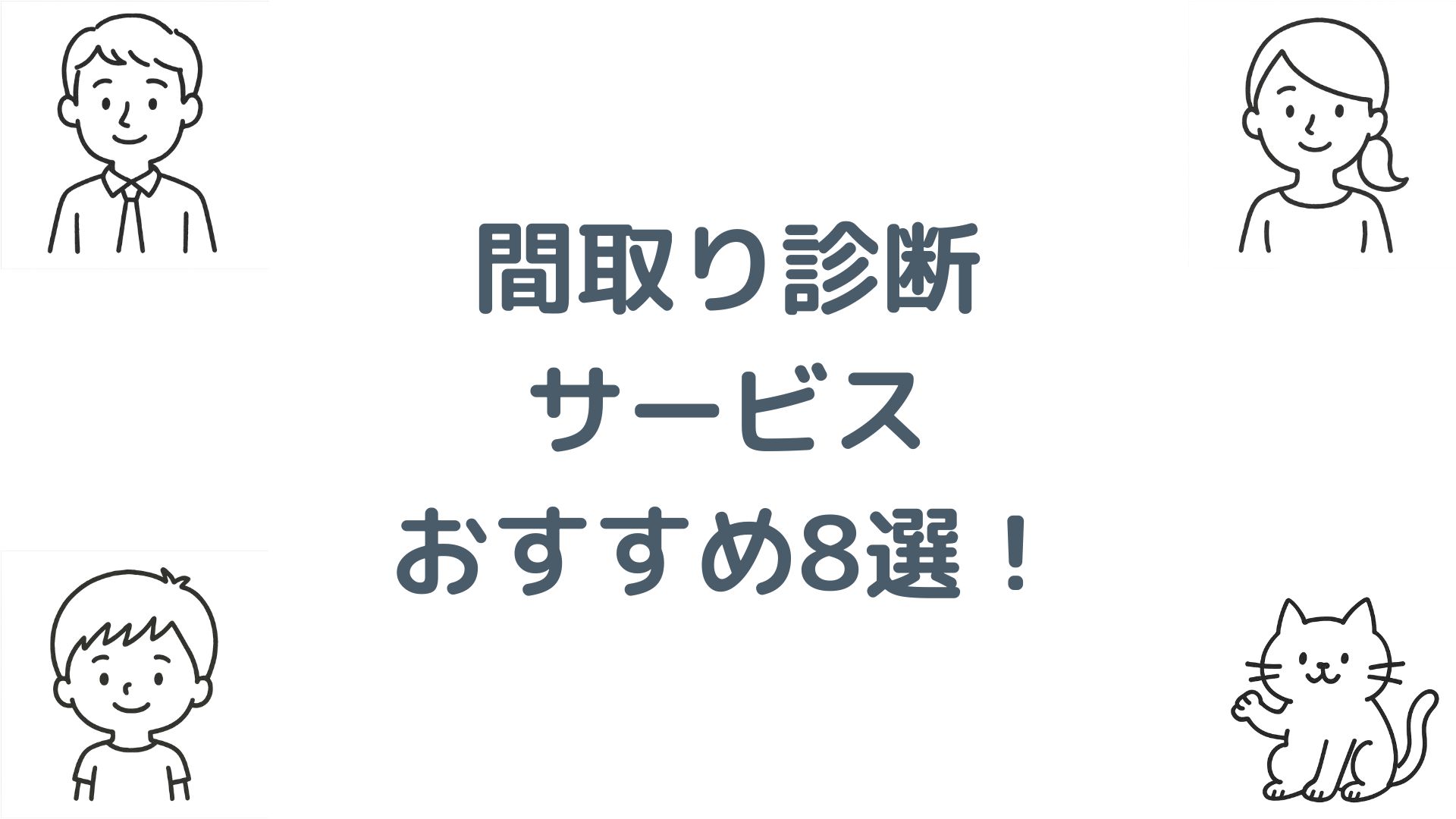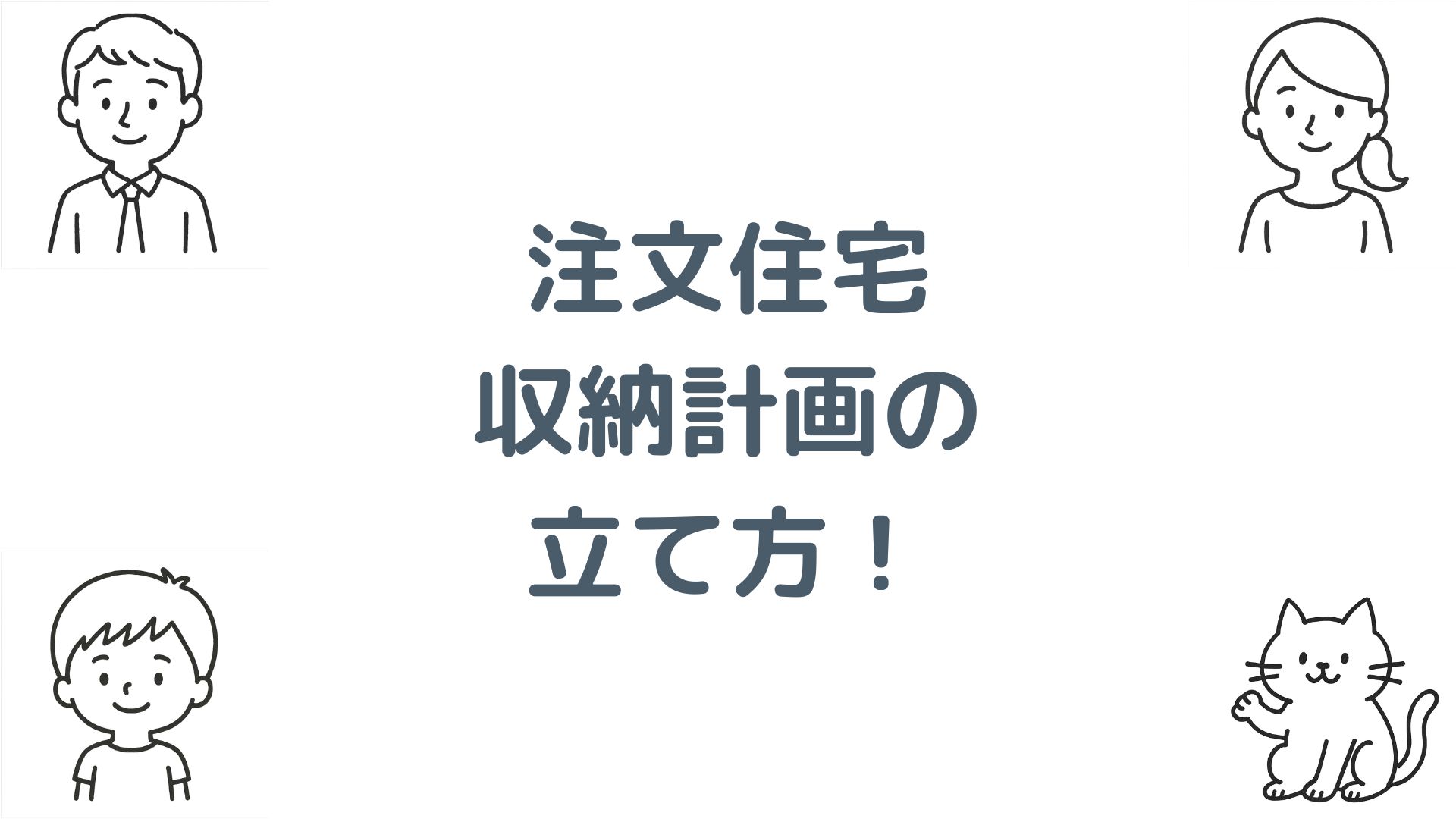今回は、洗濯導線の良い間取りについて解説していきます。
注文住宅やリノベーションを検討する際、多くの人が最優先事項として挙げるのが「家事動線」。
日々の暮らしの中で繰り返される家事は、積み重なると膨大な時間と労力になります。その中でも特に負担が大きいのが「洗濯」。
「重い洗濯カゴを持って1階と2階を往復するのが辛い」
「雨が続くとリビングが洗濯物だらけになり、くつろげない」
「取り込んだ洗濯物がソファの上に山積みで、畳む気力が起きない」
これらはすべて、間取りと動線設計の不備から生まれるストレスです。
洗濯は「洗う」だけでなく、「干す」「取り込む」「畳む」「しまう」という複数の工程を含み、家の中を移動する距離が長くなりがちな家事。
だからこそ、間取りの工夫一つで劇的に楽にすることができるのです。
この記事では、「洗濯導線」に特化し、家事が驚くほど楽になる間取りの考え方から、近年大人気のランドリールームやファミリークローゼットの具体的な活用法、絶対に避けたい失敗事例まで、網羅的に解説します。
これを読めば、あなたのライフスタイルに最適な「家事ラク間取り」の正解が見つかるはずです。
間取りで後悔だらけを防ぐ!注文住宅の失敗例と対策を徹底解説!
目次
- なぜ洗濯導線が間取りの最重要課題なのか
- 洗濯導線の間取りアイデア!劇的に良くする3つを紹介
- 洗濯導線の間取り実例【ライフスタイル別】
- 洗濯導線の間取りが決まったら導入すべき設備4選
- 洗濯導線・間取りの落とし穴と対策【失敗しないために】
- 洗濯導線の良い間取りに関するQ&A
- Q1. 家が狭くてランドリールームを作る余裕がないんだけど、どうすればいい?
- Q2. ランドリールームを作ると、建築費用ってどれくらい高くなるの?
- Q3. 「乾太くん」を入れたいけど、ガス代が高そうで心配。オール電化でも入れられる?
- Q4. ドラム式洗濯機の乾燥機能だけで十分じゃない?わざわざ部屋を作る必要ある?
- Q5. 室内干しだと、どうしても生乾きの臭いがしそうで不安なんだけど…。
- Q6. ファミリークローゼットって、年頃の子供が嫌がったりしない?
- Q7. 結局、天気のいい日は外に干したくなりそう。外干し動線も残すべき?
- Q8. 今住んでる家のリフォームでも洗濯導線って良くできる?
- Q9. ランドリールームのコンセントって、具体的にどこにいくつ必要?
- Q10. 図面を見ても、本当に使いやすいかイメージできない…。どう確認すればいい?
- Q11. 「ランドリールームは結局いらなかった」って後悔する人の理由は?
- Q12. 30坪くらいの家だと、ランドリールームを作るのは贅沢?狭くならない?
- Q13. ランドリールームとファミリークローゼット、どう繋げるのが正解?
- Q14. 2階建てなんだけど、洗濯機を2階に置くのってアリ?
- Q15. 「3畳」のランドリールームって狭くない?何が置けるの?
- 洗濯導線の良い間取りまとめ
なぜ洗濯導線が間取りの最重要課題なのか
家づくりにおいて「広々としたリビング」や「おしゃれなキッチン」に目が向きがちですが、実際に住み始めてからの満足度を左右するのは、地味ながらも毎日使う「裏方の動線」です。
まずは、洗濯導線を整えることの本質的な価値について深掘りします。
1. 洗濯は移動と工程が最も多い家事
料理は基本的にキッチン内で完結しますが、従来の洗濯はそうはいきません。
【洗濯の工程8つ】
- 脱ぐ(お風呂・各個室)
- 洗う(洗面脱衣所)
- 運ぶ(重い濡れた衣類を持って移動)
- 干す(バルコニーや庭)
- 取り込む(再び移動)
- 畳む(リビングや和室)
- 運ぶ(各個室のクローゼットへ)
- しまう(収納)
このように、洗濯には8つもの工程があり、家の中を縦横無尽に移動します。
動線が悪い間取りでは、この一連の流れだけで1日に数百歩、年間で見れば何十キロもの無駄な移動を強いられることに。
洗濯導線を最適化することは、この無駄な移動を「ゼロ」に近づける作業なのです。
2. 「名もなき家事」を消滅させる効果
洗濯には「洗って干す」以外にも、「洗剤を詰め替える」「洗濯ネットを探す」「ハンガーを揃える」「生乾きの臭いを気にする」といった、細かいストレス(名もなき家事)が付きまといます。
洗濯導線が良い間取りは、収納の配置や設備の選定も含めて計画されるため、これらの細かいストレスも同時に解消。
必要なものが手の届く場所にあり、天候を気にせず干せる環境が整えば、洗濯は「単純作業」へと変わり、精神的な負担が激減します。
3. 家族全員が当事者になれる環境づくり
「お母さん、僕の靴下どこ?」
洗濯導線が整理されていない家では、洗濯担当者(多くは妻や夫のどちらか)しか物のありかを知らないという状況になりがちです。
しかし、動線がシンプルで、「脱いだらここに入れる」「乾いたらここに戻す」という仕組みが間取りとして可視化されていれば、家族全員が自然と洗濯に参加できるようになります。
子供が自分で服を出して着替えたり、畳んだタオルをしまったりする習慣づけにも、良い間取りは大きく貢献します。
洗濯導線の間取りアイデア!劇的に良くする3つを紹介
洗濯導線を改善するためには、従来の「洗濯機は洗面所、干すのはベランダ」という固定観念を捨て、現代のライフスタイルに合わせた新しい間取りを取り入れる必要があります。
ここでは、特に効果の高い3つのアイデアを詳しく解説します。
1. 【ランドリールーム】洗う・干す・畳むを1室で完結
近年、注文住宅で採用率が急上昇しているのが「ランドリールーム」。これは洗濯に関する作業を一手に引き受ける専用の部屋のことです。
ランドリールームの定義とメリット
ランドリールームとは、洗濯機置き場に加え、室内物干しスペース、作業用カウンター、収納棚などを備えた3〜4畳程度の空間を指します。
最大のメリットは、洗濯物がリビングや居室に侵出しないこと。
急な来客があっても、ランドリールームの扉を閉めれば生活感を隠せますし、除湿機やサーキュレーターを常設して効率的に乾燥させることも可能です。
広さ別・できることの目安
2畳(コンパクト型):
洗濯機と天井吊り下げ物干し1本、スリムな収納棚が限界。乾燥機(乾太くんなど)をメインにする場合に適しています。「干す」スペースとしては手狭ですが、洗面脱衣所と兼ねるなら最低限機能します。
3畳(標準型):
洗濯機、物干しポール2本、畳むための作業台、収納棚を配置可能。4人家族の1日分の洗濯物を干すことができます。最も使い勝手が良く、人気のサイズです。
4畳以上(多機能型):
さらにアイロンがけスペースや、下着・パジャマだけでなく日常着も収納できるファミリークローゼット機能を一部持たせることができます。
失敗しない配置のコツ
ランドリールームは、日当たりや風通しを気にして南側に配置したくなりますが、実は「北側」や「家の中心」でも問題ありません。
現代の室内干しは、日光ではなく「風(空調)と除湿」で乾かすのが主流だからです。
むしろ直射日光による衣類の変色を防げます。重要なのは方角よりも、キッチンや洗面所からのアクセスが良いことです。
2. 【ファミリークローゼット】しまう動線を最短にする革命
洗濯で最も面倒な「各部屋へ配る」作業をなくすのが、ファミリークローゼット(以下、ファミクロ)。
ファミクロの役割と種類
ファミクロとは、家族全員の衣類を一箇所にまとめて管理する収納スペースです。
- ウォークインタイプ:
部屋のように中に入って使うタイプ。収納力は高いですが、行き止まりになるため、空気の入れ替えや動線に注意が必要です。 - ウォークスルータイプ:
出入り口が2つあり、通り抜けできるタイプ。「洗面所から入って、着替えて、廊下へ出る」といった回遊動線の一部として機能させるのに最適。
配置のベストプラクティス
最も効率的なのは、ランドリールームのすぐ隣(または直結)に配置すること。
「乾いた洗濯物をハンガーのまま数歩移動させて掛けるだけ」という究極の時短が実現します。
また、1階に配置することで、帰宅後に「洗面所で手洗い→ファミクロで部屋着に着替え→リビングへ」という帰宅動線ともリンクさせることができ、リビングに脱ぎ散らかされた服やバッグがなくなります。
ただし、全ての服を1階に置くとスペースが足りなくなる可能性があるため、「オンシーズンの服と下着は1階ファミクロ、オフシーズンの服や冠婚葬祭用は2階の各個室」というように使い分けるのが現実的です。
3. 【回遊動線】行き止まりをなくして家事を止めない
家の中に行き止まりを作らず、ぐるりと回れる「回遊動線」を取り入れることで、洗濯効率はさらに上がります。
キッチン・洗面・ランドリーをつなぐ
例えば、キッチンの右側から洗面所へ行け、左側からリビングへ行けるような間取りです。
料理中に洗濯終了のブザーが鳴ったら、最短ルートでランドリールームへ移動して干し作業を開始できます。
また、朝の忙しい時間帯、誰かが洗面所を使っていても、別のルートからトイレやお風呂へ行けるため、家族間の動線渋滞(カチ合い)を防げます。
玄関からの裏動線(どろんこ動線)
小さなお子さんがいる家庭や、アウトドアが趣味の家庭におすすめなのが、玄関から直接洗面所・浴室へ行ける動線です。
帰宅して汚れた服をすぐに洗濯機に入れ、そのままお風呂へ直行できるルートを確保することで、リビングを汚さずに済みます。
この動線上に予洗い用のスロップシンクがあれば完璧です。
洗濯導線の間取り実例【ライフスタイル別】
「良い間取り」に絶対的な正解はありません。生活スタイルや家族構成、敷地の条件によって最適解は異なります。
ここでは具体的なシチュエーション別の間取り戦略を紹介します。
1. 【共働き・子育て世帯】時短・効率最優先プラン
時間が何よりも貴重な共働き世帯には、「1階完結型」かつ「室内干し特化」の間取りがおすすめです。
- 間取りの特徴:
キッチン横にランドリールームとファミクロを一直線に配置。朝、出勤前に洗濯機を回して室内干しをし、帰宅後は取り込んでその場で畳んでしまう。 - ポイント:
外干しを諦め、ガス衣類乾燥機(乾太くん)や高性能な除湿機を導入することで、「干す時間」そのものを短縮します。夜洗濯派にも対応できるよう、脱衣所と洗面所は扉で仕切れるようにし、家族が入浴中でも気兼ねなく洗濯作業ができるように配慮します。
2. 【30坪前後のコンパクトハウス】空間活用型プラン
限られた坪数でランドリールームを作るのは難しい場合があります。その場合、「兼用スペース」を賢く使うのが鍵です。
- 間取りの特徴:
独立したランドリールームは作らず、洗面脱衣所を少し広め(3畳)にとります。天井には昇降式の物干し竿を設置し、洗面台の下や壁面をフル活用して収納を確保。 - ポイント:
廊下を極力減らし、洗面所を廊下兼用のスペースとして捉えることも一つの手。また、階段上のホールや2階の廊下を広げて室内干しスペースにするなど、デッドスペースを活用します。
3. 【外干し派・2階リビング】日当たり重視プラン
「洗濯物は太陽の光で乾かしたい」という強いこだわりがある場合や、日当たりの良い2階にリビングがある場合の間取りです。
- 間取りの特徴:
浴室と洗面所(洗濯機)を2階に配置。洗濯機からバルコニーまでの距離がゼロになり、重い洗濯物を持って階段を上がる必要がありません。 - ポイント:
取り込んだ洗濯物をどこで畳むかを計画しておく必要があります。2階リビングの畳コーナーや、バルコニーに隣接したホールにカウンターを設けるのがおすすめ。ただし、1階の寝室から着替えを取りに2階へ上がる手間が発生するため、1階にも小さなクローゼットを設けるか、2階にファミクロを作るか検討が必要です。
4. 【シニア・平屋】バリアフリー・安全重視プラン
将来を見据えた平屋や、シニア世代の間取りでは、安全性と移動距離の短さが最優先です。
- 間取りの特徴:
寝室の近くに水回りとトイレを集約。洗濯物はウッドデッキなどの低い位置で干せるようにし、高い位置への物干し作業を減らします。 - ポイント:
ヒートショック対策として、ランドリールームや脱衣所もリビングと同じ室温になるよう断熱・空調計画を徹底。また、洗濯機から物干し場までの床は段差をなくし、滑りにくい素材を選びます。
洗濯導線の間取りが決まったら導入すべき設備4選
間取りが決まったら、次は設備選び。適切な設備を導入することで、洗濯導線の機能性はさらに向上します。
1. ガス衣類乾燥機「乾太くん」
現代の洗濯革命とも言える設備。コインランドリー並みのパワーで、5kgの洗濯物を約50分で乾燥させます。
- 導入のメリット: 「干す」作業が消滅。タオルがホテル並みにふわふわになり、生乾き臭もありません。
- 設計の注意点: 排湿筒(ダクト)を屋外に出す工事が必要なため、設計段階で設置場所を決めておく必要が。また、本体の上に収納棚を作るか、専用台を使うかによって使い勝手が変わります。
2. スロップシンク(多目的流し)
ランドリールームや洗面所に設置する、深型の流し台。
- 用途: 子供の上履き、泥だらけのユニフォーム、汚れた雑巾、予洗いが必要な衣類などを、洗面ボウルを使わずにガシガシ洗えます。つけ置き洗いにも便利。
- 注意点: お湯が出る混合水栓にすることを強く推奨します。冬場の泥汚れ落としが水だけでは辛いためです。
3. 室内物干しユニット
- 昇降式(ホスクリーン・ホシ姫サマなど): 使わない時は天井に収納でき、干す時だけ手元まで降ろせるため、空間を邪魔しません。電動式と手動式があります。
- ワイヤー式(pid4Mなど): 壁からワイヤーを引き出して使うタイプ。見た目が非常にシンプルでミニマルな空間に合います。
- 固定式アイアンバー: 天井に常設する黒や白のアイアンバー。おしゃれなインテリアの一部として見せることができ、観葉植物を吊るすのにも使えます。
4. コンセントと換気設備の計画
ランドリールームには、想像以上に多くのコンセントが必要です。
- コンセント: 除湿機、サーキュレーター、アイロン、冬場のヒーター、扇風機、充電式掃除機の基地など。足元だけでなく、棚の上やカウンターの高さにも設置しましょう。
- 換気扇・窓: 湿気対策には、空気の流れを作ることが重要。給気口と排気口(換気扇)の位置を対角線上に配置し、空気が部屋全体を流れるようにします。窓を開けて換気したい場合は、防犯面を考慮して高窓(ハイサイドライト)や横滑り出し窓がおすすめ。
洗濯導線・間取りの落とし穴と対策【失敗しないために】
良かれと思って採用した間取りが、住んでみると不便だったというケースは少なくありません。
ここでは、よくある失敗事例とそれを回避するための対策を紹介します。
失敗1:ランドリールームを作ったが、湿気でカビが生えた
【原因】
日当たりを重視して南側に作ったが、気密性が高すぎて湿気が逃げず、換気計画も不十分だった。
または、部屋干しの量に対して部屋の容積が小さすぎた。
【対策】
ランドリールームには必ず強力な換気扇を設置し、サーキュレーターで空気を循環させます。
壁材には調湿機能のある「エコカラット」や「珪藻土クロス」を採用するのも有効。
また、除湿機を24時間稼働させることを前提とした排水設備(ドレン排水)を壁に仕込んでおくと、水捨ての手間がなくなります。
失敗2:広すぎて物置化してしまった
【原因】
「広い方がいいだろう」と4畳以上のスペースを確保したが、具体的な使い道をシミュレーションしていなかったため、とりあえず物を置く場所になってしまった。
【対策】
必要な広さは「洗濯物の量」と「作業内容」で決まります。単に干すだけなら2〜3畳で十分です。
アイロンがけをする、PC作業もするなど、用途を明確にしてから広さを決めましょう。あえて広すぎない方が、こまめに片付ける習慣がつきます。
失敗3:動線が交錯して朝の渋滞が起きる
【原因】
キッチン、洗面所、ランドリールームを一直線に並べたが、通路幅が狭く、朝の支度をする家族と洗濯をする人がぶつかってしまう。
【対策】
通路幅は最低でも90cm、できれば100〜120cm確保します。
また、洗面台を脱衣所から出して廊下やホールに設置する「独立洗面台」にすることで、誰かがお風呂に入っていても、洗濯をしていても、気兼ねなく歯磨きや手洗いができます。
失敗4:収納の奥行きが深すぎて使いにくい
【原因】
ランドリールームやファミクロの収納棚の奥行きを深くしすぎたため、奥の物が取り出しにくく、手前に物が積み上がってしまった。
【対策】
タオルや洗剤、畳んだ衣類を収納する場合、棚の奥行きは30cm〜40cmあれば十分。深すぎる収納は「死蔵品」を生む原因になります。
可動棚にして、収納ボックスのサイズに合わせて高さを変えられるようにするのがベストです。
失敗5:コンセントの位置が悪く、除湿機のコードが邪魔
【原因】
壁の隅にコンセントを作ったが、洗濯物を干すと除湿機を置きたい場所(洗濯物の真下)までコードが届かず、延長コードを使う羽目になった。
【対策】
物干しポールの配置を決めてから、その真下や横にコンセントを配置します。
コードにつまずかないよう、床用コンセント(フロアコンセント)を採用するのも一つの手です。
洗濯導線の良い間取りに関するQ&A
洗濯導線の良い間取りに関するQ&Aに回答していきます。
Q1. 家が狭くてランドリールームを作る余裕がないんだけど、どうすればいい?
A1. 無理に専用の部屋を作る必要はありません。洗面脱衣所を通常より0.5〜1畳広げるだけでも室内干しスペースは確保できます。
また、廊下や階段ホールを広めにとって物干しワイヤーを設置するなど、「通路」を兼ねたスペース活用も有効です。
まずは「兼用」できる場所がないか探してみましょう。
Q2. ランドリールームを作ると、建築費用ってどれくらい高くなるの?
A2. おおよその目安ですが、床面積が増える分、30〜50万円程度の増額になることが一般的です。
ただし、その分「ベランダ」や「勝手口」をなくしたり、廊下を減らしたりすることで総予算を調整することも可能です。
洗濯の手間が減る=「時間を買う」投資として、トータルで判断することをおすすめします。
Q3. 「乾太くん」を入れたいけど、ガス代が高そうで心配。オール電化でも入れられる?
A3. ガス代は1回あたり約40〜60円程度が目安で、コインランドリーより遥かに安価です。
オール電化住宅でもプロパンガスなどを個別契約すれば導入可能ですが、ガスの基本料金が別途かかります。
初期費用とランニングコストのバランスを工務店とシミュレーションしてみてください。
Q4. ドラム式洗濯機の乾燥機能だけで十分じゃない?わざわざ部屋を作る必要ある?
A4. ドラム式も優秀ですが、乾燥まで行うと1回3〜4時間かかり、1日複数回回す家庭では時間が足りなくなることがあります。
また、シワになりやすい服や乾燥機NGの服は結局干す必要があります。
「干す場所」をゼロにするのは難しいため、最低限の物干しスペースは確保しておくと安心です。
Q5. 室内干しだと、どうしても生乾きの臭いがしそうで不安なんだけど…。
A5. 臭いの原因は「乾くまでの時間」にあります。
サーキュレーターで風を当て続け、除湿機で湿度を下げれば、外干し以上に早く乾き、臭いも発生しません。
コツは、ランドリールームを閉め切って狭い空間で除湿機をフル稼働させることです。
Q6. ファミリークローゼットって、年頃の子供が嫌がったりしない?
A6. 確かに思春期になると個室で管理したがるお子さんもいます。
おすすめは、下着やパジャマ、制服などの「毎日使うもの」だけをファミクロに置き、私服は個室へ、という運用ルールです。
また、ファミクロ内に個人ごとのロッカーや引き出しを用意し、プライバシーを確保する工夫も有効です。
Q7. 結局、天気のいい日は外に干したくなりそう。外干し動線も残すべき?
A7. 完全に外干しをなくすのが不安であれば、ランドリールームから直接出られる「掃き出し窓」や「勝手口」を設けておくと良いでしょう。
デッキを設置すれば、重い洗濯物を持って段差を降りる必要もなくなります。「基本は室内、気分転換に外」という両立スタイルも人気です。
Q8. 今住んでる家のリフォームでも洗濯導線って良くできる?
A8. 可能です。壁を壊して間取りを変える大規模リフォームでなくとも、洗面所にガス衣類乾燥機を後付けしたり、壁付けの物干しユニットを設置したりするだけで劇的に変わります。
まずは「干す場所」と「畳む場所」を近づける工夫から始めてみましょう。
Q9. ランドリールームのコンセントって、具体的にどこにいくつ必要?
A9. 失敗しやすいポイントです。
最低でも「除湿機用」「サーキュレーター用(高い位置や棚上)」「暖房器具・扇風機用」「アイロン用(作業台近く)」「充電式掃除機の充電用」の5口以上は確保してください。
除湿機はずっとつけっぱなしになるため、足元で邪魔にならない位置計画が重要です。
Q10. 図面を見ても、本当に使いやすいかイメージできない…。どう確認すればいい?
A10. 図面の上に指を置いて、朝起きてから寝るまでの自分の動きをなぞってみてください。
「ここで濡れたタオルを持って、ドアを2回開けて…」と具体的にシミュレーションすると、無駄な動きが見えてきます。
特に「洗濯機の前」と「干す場所」の通路幅が狭すぎないか(人がすれ違えるか)は要チェックです。
Q11. 「ランドリールームは結局いらなかった」って後悔する人の理由は?
A11. よくある後悔の原因は「乾きにくい」「狭くて作業しづらい」「動線が悪くて結局リビングに干している」の3点です。
特に、換気計画が甘くて生乾き臭がしたり、他の家事エリアから遠すぎて孤立した部屋になると使わなくなります。
「ただ部屋を作る」のではなく、「どう乾かすか」「どう動くか」をセットで考えることが成功の鍵です。
Q12. 30坪くらいの家だと、ランドリールームを作るのは贅沢?狭くならない?
A12. 30坪でも工夫次第で実現可能です。
コツは「兼用」すること。独立した部屋を作ろうとするとLDKが圧迫されますが、洗面脱衣室を「ランドリー兼脱衣室」として3〜3.5畳確保すれば十分機能します。
廊下を減らしてスペースを捻出するプランが、30坪前後の住宅では定石です。
Q13. ランドリールームとファミリークローゼット、どう繋げるのが正解?
A13. 理想は「ランドリールーム→ファミリークローゼット→リビング(または廊下)」と抜けられるウォークスルー配置です。
これなら「乾いた服をハンガーのまま数歩で移動して収納」し、そのまま着替えてリビングへ出るという無駄のない動線が完成します。湿気がクローゼットに流れないよう、間に扉を設けるのをお忘れなく。
Q14. 2階建てなんだけど、洗濯機を2階に置くのってアリ?
A14. 「外干し派」なら大いにアリです。洗濯機からバルコニーへの動線がゼロになり、濡れた重い洗濯物を持って階段を上がる重労働から解放されます。
ただし、料理と洗濯を同時進行したい場合は1階と2階を行き来することになるため、ご自身の家事スタイル(まとめて洗うか、隙間時間で洗うか)に合わせて慎重に検討してください。
Q15. 「3畳」のランドリールームって狭くない?何が置けるの?
A15. 実は3畳は、洗濯機・乾燥機・スロップシンク・作業カウンター・収納棚をすべて配置できる「黄金サイズ」です。
4人家族の洗濯物も干せるスペースが確保でき、広すぎず掃除も楽なので、最も推奨される広さの一つです。
2畳だと少し工夫が必要、4畳だとファミリークローゼット機能も持たせられる、という目安で考えてみてください。
洗濯導線の良い間取りまとめ
今回は、洗濯導線の良い間取りについて解説しました。
洗濯導線の良い間取りは、単なる「時短」だけでなく、日々の暮らしに精神的なゆとりをもたらします。
最後に、これまでの内容を踏まえ、実際に間取りを検討する際のステップを整理します。
ステップ1:現状の不満と理想の洗い出し
現在の住まいで、洗濯のどの工程にストレスを感じているか書き出してみましょう。
- 「干す場所が狭い」
- 「取り込んだ後、畳まず放置してしまう」
- 「夜洗濯したいが音が気になる」
など、不満の中に理想の間取りのヒントがあります。
ステップ2:スタイルの決定
自分たちのライフスタイルに合わせて、基本方針を決めます。
- 外干し派 vs 室内干し派(または乾燥機派)
- 毎日洗濯派 vs 週末まとめ洗い派
- 畳む派 vs ハンガー収納派
ステップ3:配置の検討と動線シミュレーション
図面上で指を動かしながら、シミュレーションを行います。
- 汚れた服を持って洗濯機へ行く
- 洗い終わった服を取り出して干す
- 乾いた服をしまう
この一連の動きに無理がないか、重いものを持って長い距離を歩かないかを確認します。ランドリールームやファミクロの導入もこの段階で検討します。
ステップ4:収納と設備の詳細設計
収納したい物の量を具体的に測り、棚のサイズや位置を決めます。乾太くんやスロップシンクなど、後付けが難しい設備はここで確定させます。
ステップ5:プロへの相談
自分たちの要望が固まったら、ハウスメーカーや工務店の設計士に伝えます。
その際、「ランドリールームが欲しい」だけでなく、「夜に洗濯をして室内干しで完結させたいから、ランドリールームが欲しい」というように、「どう暮らしたいか」という目的を伝えることが重要です。
プロならではの視点で、換気計画や構造的な制約を踏まえた最適な提案をしてくれるはず。洗濯は一生続く家事。
だからこそ、妥協せずに徹底的にこだわり、あなたの家族にとって最高の「家事ラク間取り」を実現してください。
それが、長く愛せる住まいへの第一歩となるでしょう。
間取りで後悔だらけを防ぐ方法!注文住宅の失敗例と対策を徹底解説
-

-
間取りで後悔だらけを防ぐ方法!注文住宅の失敗例と対策を徹底解説
続きを見る
間取り診断サービスおすすめ8選を紹介!セカンドオピニオンの選び方と費用相場は?
-

-
間取り診断サービスおすすめ8選を紹介!セカンドオピニオンの選び方と費用相場は?
続きを見る
注文住宅の収納計画の立て方!後悔しない間取りを実現する4つのステップと場所別アイデアを解説!
-

-
注文住宅の収納計画の立て方!後悔しない間取りを実現する4つのステップと場所別アイデアを解説!
続きを見る