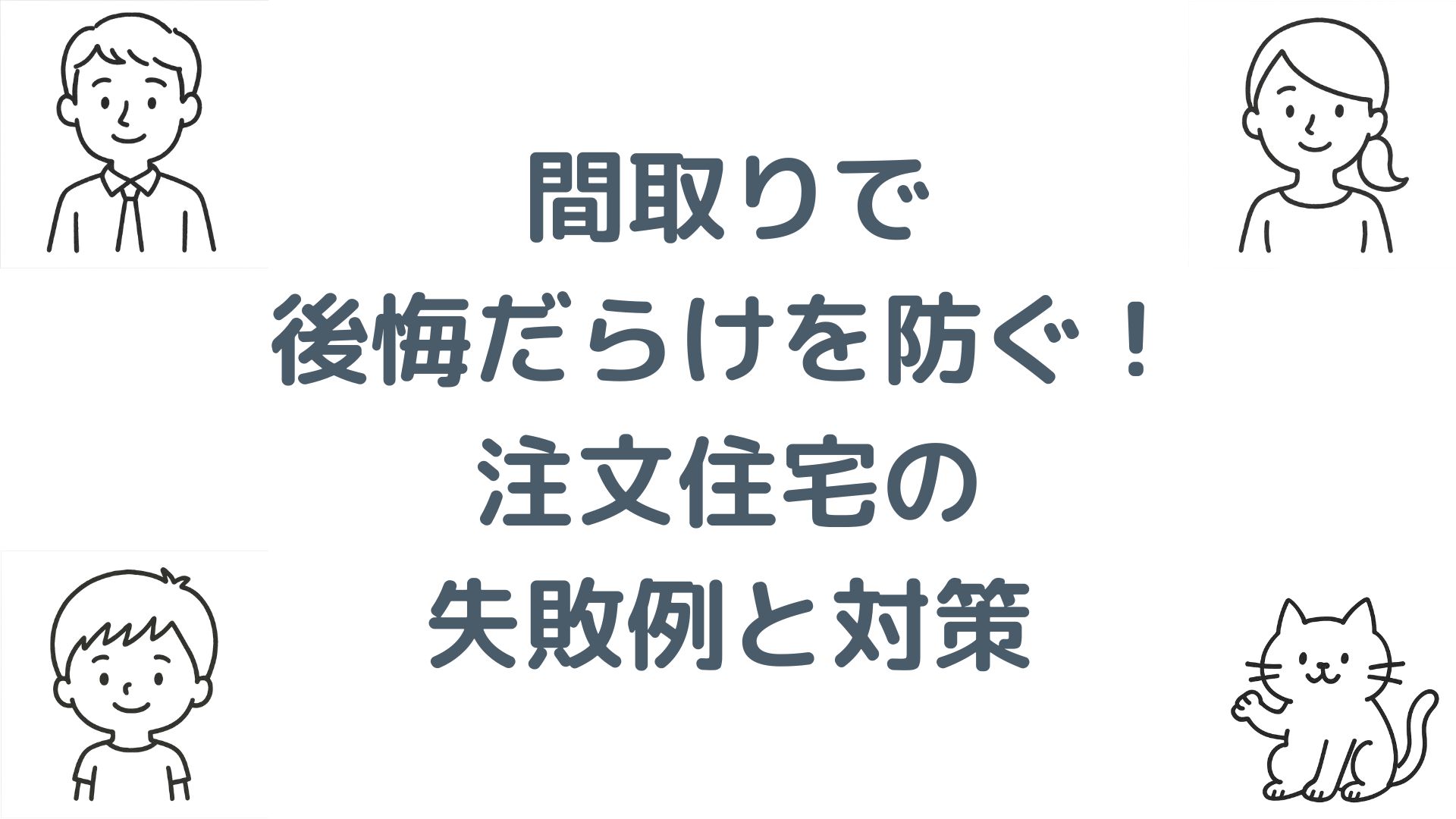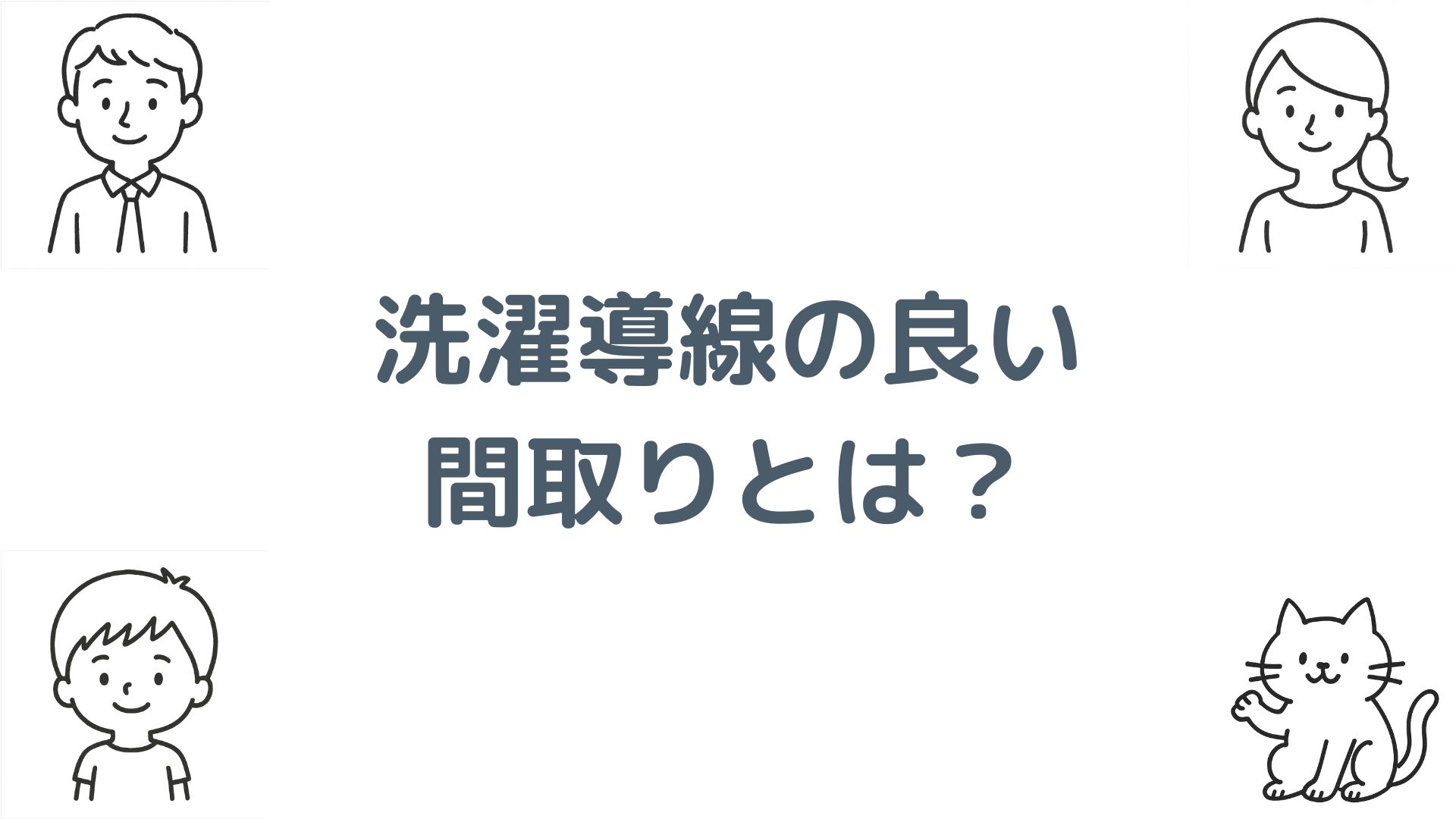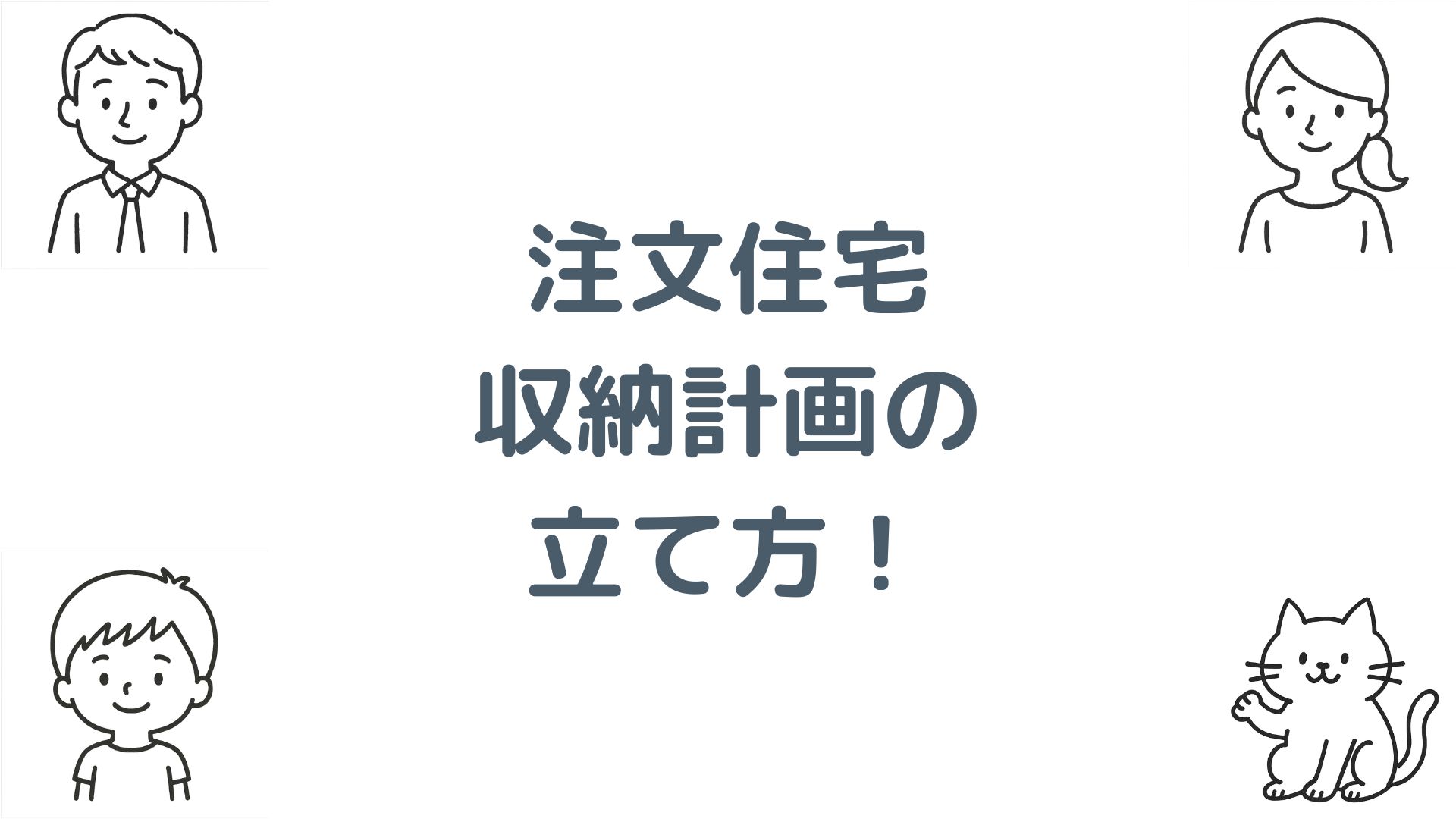こんな方におすすめ
今回は、間取り診断サービスのおすすめについて解説していきます。
「一生に一度の家づくり、本当にこの間取りで後悔しない?」
「ハウスメーカーから提案された図面、なんとなくしっくりこないけれど、どこを直せばいいかわからない」
数千万円という大きな買い物だからこそ、契約直前になって不安が押し寄せてくるのは当然のことですよね。
そんな時に活用したいのが、プロの建築士による「間取り診断(セカンドオピニオン)」です。
自分たちや担当の営業マンだけでは気づけなかった「暮らしにくさ」や「改善点」を、第三者の視点でズバリ指摘してもらえるこのサービスは、失敗しない家づくりのための「最後の砦」とも言えます。
本記事では、間取り診断のメリットや依頼すべきタイミング、そして無料から有料までのおすすめサービスを徹底解説します。
あなたの家づくりを成功に導くためのパートナー選びに、ぜひお役立てください。
間取りで後悔だらけを防ぐ!注文住宅の失敗例と対策を徹底解説!
目次
- 間取り診断(セカンドオピニオン)サービスおすすめ8選を紹介!
- 間取り診断(セカンドオピニオン)をおすすめする5つの理由【家づくりでなぜ必要?】
- 間取り診断(セカンドオピニオン)の依頼におすすめなタイミングは?
- 間取り診断(セカンドオピニオン)の費用相場とサービスの違い【無料と有料どっちがいい?】
- 間取り診断(セカンドオピニオン)を依頼する前に知っておくべき3つの注意点
- 間取り診断サービスのおすすめに関するQ&A
- Q1. 診断をお願いするときって、図面のほかに何を用意すればいいの?
- Q2. 診断してもらった結果を、そのままハウスメーカーの担当者に見せても大丈夫?
- Q3. 申し込んでから結果が来るまで、大体どれくらいの日数がかかる?
- Q4. 家事動線だけじゃなくて、風水とか家相も見てほしいんだけど対応してる?
- Q5. 数千円で頼める安いサービスって、本当に役に立つの?安すぎて不安……。
- Q6. 提案してもらった間取りが、実際には建てられないことってあるの?
- Q7. 図面のデータがないんだけど、スマホで撮った写真でも依頼できる?
- Q8. 診断結果を見て「なんか違うな」って思ったら、修正や質問は追加でできる?
- Q9. もう契約しちゃった後なんだけど、今から診断してもらう意味ってあるかな?
- Q10. 結局、どこに頼むか迷う……。一番失敗しない選び方は?
- Q11. 診断をお願いしてる間に、工事の予定が遅れちゃったりしない?
- Q12. 「これだけはやめとけ」っていう、住んではいけない間取りってある?
- Q13. アプリで自分で間取りを作ってみるのってどう?おすすめはある?
- Q14. 最近話題のAI(人工知能)で間取り診断ってできないの?
- Q15. 今みんなが採用してる、人気の間取りランキングってどんなの?
- 間取り診断サービスおすすめまとめ:「後悔しないための必要経費」で納得のいく家づくりを!
間取り診断(セカンドオピニオン)サービスおすすめ8選を紹介!
まずは、数ある間取り診断サービスの中から、特に評判が良く利用価値の高い8つのサービスをご紹介します。
それぞれの特徴を比較して、ご自身の状況に合ったものを選んでください。
① タウンライフ家づくり

まだ特定のハウスメーカーと契約しておらず、広く情報を集めたい段階の方に最適な無料の一括請求サービス。
【特徴】
- 無料でのプラン提案: 希望の条件や要望を入力するだけで、登録している複数のハウスメーカーや工務店から、オリジナルの間取りプランと見積もりが無料で届く
- 比較検討に最適: 「A社の間取りは気に入ったけど予算オーバー、B社は安いけど間取りが微妙」といったように、各社の提案力を横並びで比較することができる。自分たちの相場観を養うのにも役立ちます
【おすすめな人】
- まだ土地が決まっていない、あるいはメーカー選びの初期段階の人
- 無料で色々な会社の間取りアイデアを見てみたい人
- 間取りだけでなく、資金計画(見積もり)も含めて検討したい人
▼希望条件に合った会社だけが届くから安心
② ココナラ

日本最大級のスキルマーケット「ココナラ」は、間取り診断を探す際にまずチェックすべきプラットフォーム。
多くの一級建築士やインテリアコーディネーター、住宅設計のプロが出品しており、手軽に依頼できるのが最大の特徴です。
【特徴】
- 料金が明確: 3,000円程度の簡易診断から、50,000円前後の本格的な図面作成まで、予算に合わせてピンポイントで選べる
- 口コミが見える: 実際に利用した人の評価(星の数)や感想コメントが公開されているため、信頼できる出品者を選びやすく「ハズレ」を引くリスクが低い
- 多様な専門家: 一般的な間取り診断だけでなく、「風水を見てほしい」「収納計画だけ見てほしい」「パース(完成予想図)を作ってほしい」といったニッチな要望にも対応できる専門家が見つかる
【おすすめな人】
- 費用を抑えつつ、プロの意見を聞きたい人
- ハウスメーカーとの打ち合わせ期限が迫っており、スピーディーに回答が欲しい人
- 複数の専門家の意見を比較してみたい人
③ みゆう間取り相談室

神戸にある一級建築士事務所「みゆう設計室」が運営する間取り相談サービス。
主婦であり母である女性一級建築士が代表を務めており、生活実感のこもった提案が強みです。
【特徴】
- 主婦・母目線での設計: ただ部屋を並べるだけでなく、「洗濯物をどこで畳むか」「子供が帰宅してからの動線」など、日々の暮らしに密着したアドバイスが得られる
- Zoom相談+間取り作成: ビデオ通話でじっくりヒアリングを行った上で改善案を作成してくれるため、施主の悩みや要望を深く理解したプランが出来上がる。不安を解消しながら理想のプランを作り上げるプロセスを重視
【おすすめな人】
- 家事動線(洗濯、料理、掃除)を徹底的に良くして、家事ラクな家を作りたい人
- 子育てのしやすさや、家族のコミュニケーションを重視した間取りを求めている人
- 女性ならではの視点で、細やかな収納計画などを相談したい人
④ 木なり設計
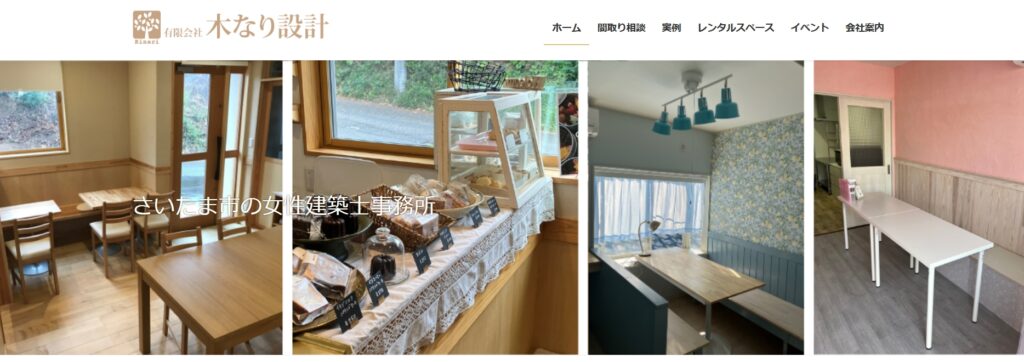
埼玉県にある設計事務所が提供する、女性建築士によるセカンドオピニオンサービス。
特に女性からの支持が厚く、きめ細やかな対応に定評があります。
【特徴】
- 女性建築士による「女性目線」: キッチン周りの使い勝手や、日々のストレスを減らす工夫など、女性建築士ならではの感性で診断を行う
- 手軽な相談スタイル: LINEやZoomを使った相談が可能で、堅苦しくなく気軽に始められる点が魅力。「ちょっとここだけ聞きたい」というニーズにも応えてくれる
【おすすめな人】
- 収納計画に不安があり、具体的に何をどこにしまうか相談したい人
- 男性の設計士には伝えにくい、生活の細かなこだわりを理解してほしい人
- 遠方の設計事務所に行くのは大変だが、オンラインでしっかり相談したい人
⑤ かえるけんちく相談所

YouTubeチャンネルなどでも精力的に情報発信を行っている、一級建築士による人気の診断サービス。論理的で分かりやすい解説が特徴です。
【特徴】
- 動画での解説: 人気プランの「プレミアム動画間取り診断PRO」では、診断結果をレポートだけでなく動画で詳しく解説してくれます。文章だけでは伝わりにくいニュアンスや、なぜその修正が必要なのかという理由が明確に理解できる
- 総合的なガチ診断: 間取りの使い勝手だけでなく、断熱性能や構造的な安全性、資産価値など、家の性能面まで含めたトータルチェックを行う
【おすすめな人】
- 絶対に後悔したくない、失敗が許されないと考える慎重派
- 断熱性能や耐震性など、目に見えない部分もプロの目でチェックしてほしい人
- 文字だけのレポートではなく、動画で分かりやすく説明してほしい人
⑥ 設計図のセカンドオピニオン
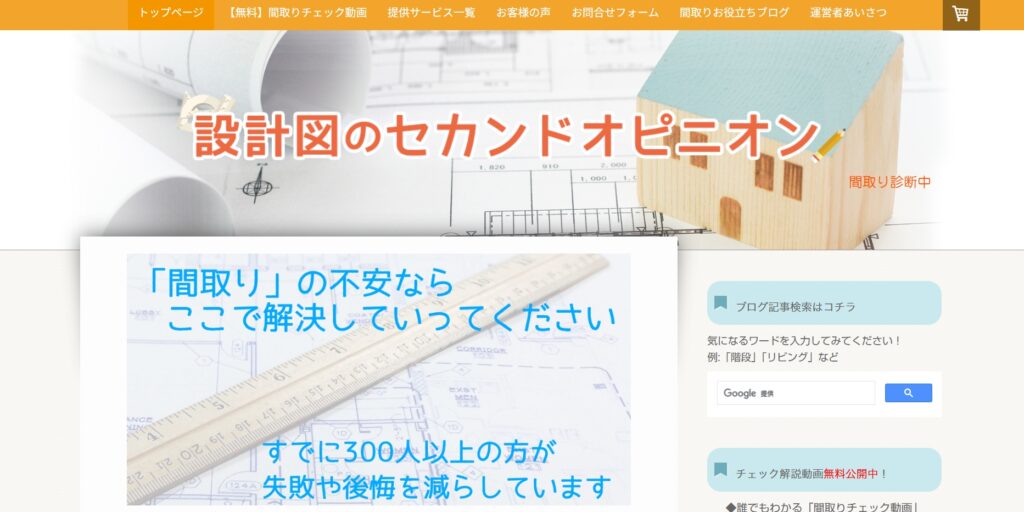
元・現場監督としての経験を持つプロが提供するサービス。
設計図面上の話だけでなく、実際に建てる際の施工リスクまで見据えたアドバイスが可能です。
【特徴】
- 施工リスクを考慮: 「図面上は描けるが、実際の工事では雨漏りのリスクが高まる」「メンテナンスが大変になる」といった、現場を知る人間ならではの視点で指摘を行う
- 新プラン提案: 現在の間取りの添削だけでなく、全く違うアプローチでの「新プラン提案」も行っている。行き詰まった現状を打破したい場合に有効
【おすすめな人】
- 今の間取りに閉塞感があり、全く違うアイデアが欲しい人
- 施工トラブルや将来のメンテナンスまで考慮した、現実的なアドバイスが欲しい人
- 予算はある程度かけても、質の高い回答を求めている人
⑦ Madree(マドリー)
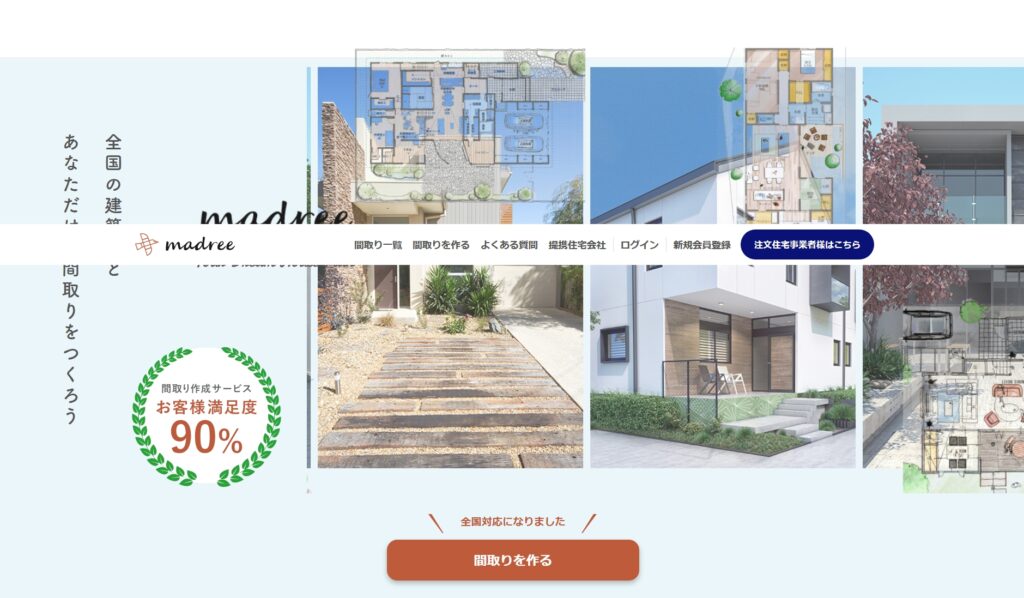
スマホで完結する、建築家による間取り作成サービス。デザイン性の高い提案が特徴。
【特徴】
- 登録建築家による作成: 全国の登録建築家が、あなたの要望に合わせて間取りを作成してくれる
- デザイン性: ハウスメーカーの画一的な間取りとは一味違う、建築家ならではの工夫やデザイン性が盛り込まれた間取りが見られる
- キャンペーン: 基本は有料サービスだが、時期によっては無料枠のキャンペーンを実施していることもある
【おすすめな人】
- おしゃれでデザイン性の高い間取りを見たい人
- ハウスメーカーの提案が平凡でつまらないと感じている人
- スマホで手軽に依頼を完結させたい人
⑧ houzz(ハウズ)

建築家と施主をつなぐマッチングサイトの機能の一部として、家づくりに関する相談掲示板が用意されています。
【特徴】
- 掲示板での無料相談: 「変形地だけどどんな家が建つ?」「この予算でこの要望は無謀?」といった疑問を掲示板に投稿すると、登録している建築家や専門家から回答がもらえる
- 素朴な疑問解消: 本格的な診断の前段階として、専門的な知識が必要な疑問を解消するのに役立つ
【おすすめな人】
- まだ依頼するほどではないが、プロの意見を少し聞いてみたい人
- 特定の図面の診断というよりは、家づくり全般の疑問を解消したい人
間取り診断(セカンドオピニオン)をおすすめする5つの理由【家づくりでなぜ必要?】
家づくりにおいて、ハウスメーカーや工務店の設計士は「家を建てるプロ」ですが、必ずしも「あなたの生活スタイルの理解者」とは限りません。
また、自社の利益や施工効率を優先した提案になりがちな側面も。そこで重要になるのが、利害関係のない第三者による「間取り診断」です。
ここでは、セカンドオピニオンを取り入れるべき具体的なメリットを5つ解説します。
理由① プロの「第三者視点」で客観的なチェックができる
自分たちで間取りを見ていると、「LDKは20畳欲しい」「アイランドキッチンがいい」といった要望(こだわり)に目が向きがちで、基本的な欠陥や不便さを見落としてしまうことが。
間取り診断では、プロが冷静な第三者の目で図面を見ます。
「このドアの位置だと家具が置けない」「廊下が狭すぎて搬入が困難」といった、素人では気づきにくい物理的な問題点を指摘してもらえるのが最大のメリットです。
理由② 家事動線や収納など「現実的な暮らしやすさ」が向上する
図面上ではきれいに納まっているように見えても、実際に生活を始めると「洗濯物を干すまでの移動が遠い」「買い物帰りにキッチンまで遠回りが必要」といった不満が出ることが。
診断サービス、特に主婦目線を持つ建築士や収納アドバイザー資格を持つプロに依頼することで、「朝起きてから寝るまでのリアルな動き」に基づいた動線チェックが可能に。
「ここに収納がないとリビングが散らかる」といった具体的なアドバイスは、住み心地に直結します。
理由③ 日当たり・風通し・構造的な無理がないかを確認できる
「南向きだから明るいはず」と思っていても、隣家の状況や窓の配置によっては、昼間でも電気が必要な暗い部屋になってしまうことが。
プロの間取り診断では、敷地条件や周辺環境(隣家の窓の位置など)も考慮して診断を行います。
また、無理な大空間を作ろうとして構造的に弱くなっていないか、耐震性に不安はないかといった専門的なチェックも期待できますよ。
理由④ ハウスメーカーへの「モヤモヤ」を解消し、自信を持って契約できる
「担当者の提案になんとなく納得がいかないけれど、プロが言うなら正しいのかな…」と、不満を飲み込んで進めてしまうのは非常に危険。
セカンドオピニオンを受けることで、「この提案は理にかなっている」と確信が得られる場合もあれば、「やはり変更した方がいい」と背中を押してもらえる場合も。
どちらにせよ、「自分で納得して決めた」という自信を持って次のステップへ進めるようになります。
理由⑤ 数百万円単位の「将来のリフォーム費用」を未然に防げる
間取りの失敗は、住んでからリフォームで直そうとすると数百万円の費用がかかることも珍しくありません。
壁を壊したり、水回りを移動させたりするのは大工事。間取り診断にかかる費用は数千円〜数万円程度です。
この「初期投資」で将来の莫大な損失リスクを回避できると考えれば、決して高い出費ではないと言えるでしょう。
間取り診断(セカンドオピニオン)の依頼におすすめなタイミングは?
間取り診断は「いつでもいい」わけではありません。
依頼するタイミングを間違えると、効果が薄れたり、かえって混乱を招いたりする可能性があります。
ベストなタイミング:ファーストプラン提案後〜契約前
最もおすすめなのは、「ハウスメーカーや工務店から、最初の間取り図(ファーストプラン)が出てきた後」です。
ある程度の叩き台があることで、診断する建築士も「施主の要望」と「施工会社の提案」のギャップを把握しやすく、具体的な改善案を出しやすくなります。
また、この段階であれば修正も比較的容易であり、ハウスメーカー側も柔軟に対応してくれる可能性が高いです。
契約後・着工直前では遅い理由
契約後、特に「着工合意(最終承認)」の直前に診断を依頼するのはリスクが高いです。
もし診断で重大な欠陥が見つかったとしても、その時点での変更は「変更契約」となり、追加費用が発生したり、工期が大幅に遅れたりする可能性があります。
また、現場監督や設計担当者との関係性が悪化する恐れも。
どうしても不安な場合を除き、できるだけ早い段階(契約前)に相談することをおすすめします。
まだ土地が決まっていない段階でも相談できる?
可能です。ただし、間取りは土地の形状や法規制(建ぺい率・容積率・斜線制限など)に大きく左右されます。
土地が決まっていない段階での相談は、「理想のライフスタイルを整理する」「必要な坪数を把握する」といった概念的なアドバイスになりがちです。
具体的な図面の添削を希望する場合は、候補地が決まってからの方が有益なアドバイスを得られます。
間取り診断(セカンドオピニオン)の費用相場とサービスの違い【無料と有料どっちがいい?】
間取り診断サービスには、無料のものから10万円を超える本格的なものまで様々です。
それぞれの特徴と費用相場を理解し、自分の目的に合ったものを選びましょう。
【無料〜数千円】手軽にアイデアが欲しい人向け(掲示板・一括請求)
- 相場: 無料
- サービス例: Yahoo!不動産(教えて!住まいの先生)、houzz、タウンライフ家づくり
- 特徴:
インターネット上の掲示板形式で質問したり、複数の会社に一括でプラン作成を依頼したりするサービス。
メリットは、コストがかからないことと、複数のプロから幅広い意見がもらえる点。
デメリットは、責任の所在が曖昧であることや、詳細な図面チェックまでは難しい点。
あくまで「アイデア出し」や「初期の比較検討」として利用するのが賢明。
【5,000円〜3万円】コスパ良くプロの意見を聞きたい人向け(スキルシェア)
- 相場: 5,000円〜30,000円
- サービス例: ココナラ、木なり設計(スポット相談)
- 特徴:
個人の建築士や設計士に直接依頼できるスキルシェアサービスが中心。
「今の図面を赤ペンで添削してほしい」「Zoomで1時間相談に乗ってほしい」といったピンポイントな利用が可能です。
メリットは、手頃な価格で有資格者の本格的なアドバイスが受けられる点。
出品者によって得意分野(デザイン重視、家事動線重視など)が異なるため、自分に合った人を選びやすいのも魅力。
デメリットは、人気の出品者は予約が取りにくいことや、あくまで個人の見解となる点。
【3万円〜10万円以上】徹底的に失敗を防ぎたい人向け(設計事務所・コンサル)
- 相場: 30,000円〜150,000円
- サービス例: みゆう間取り相談室、かえるけんちく相談所、設計図のセカンドオピニオン
- 特徴:
設計事務所などが提供する、フルパッケージの診断サービス。
図面の添削だけでなく、詳細なレポート作成、改善プランの作成、構造・温熱環境のチェック、Zoomでの長時間ヒアリングなどが含まれます。
メリットは、圧倒的な安心感と質の高さ。法的な制限から家具の配置まで、プロが全精力を注いでチェックしてくれます。
デメリットは費用がかかることですが、数千万円の家づくりにおける「保険料」と考えれば、決して高くはないでしょう。
間取り診断(セカンドオピニオン)を依頼する前に知っておくべき3つの注意点
セカンドオピニオンは非常に有効ですが、使い方を間違えるとトラブルの元になることもあります。以下の3点に注意して依頼しましょう。
注意点① ハウスメーカーの「標準仕様・工法」を確認しておく
最も重要なのがこれです。ハウスメーカーにはそれぞれ「標準仕様(ルール)」や「工法(2×4、鉄骨、木造軸組など)」があります。
例えば、診断先の建築士が「ここに窓を開けたほうがいい」と提案しても、ハウスメーカーの構造ルール(耐力壁が必要な場所など)では「物理的に不可能」な場合が。
依頼する際は、必ず「現在検討中のハウスメーカー名」や「工法」を伝え、可能であれば「ハウスメーカーのルール範囲内での改善案」を求めたほうが、実現可能性の高いアドバイスが得られます。
注意点② 「診断結果=絶対」ではない!最終決定権は自分にある
診断士の先生はプロですが、あなたの生活のすべてを知っているわけではありません。
提案された改善案が、必ずしもあなたにとって正解とは限らないのです。
例えば、「家事動線を優先して廊下を減らす」提案があったとしても、あなたが「ゆとりのある廊下が欲しい」と思っているなら、無理に採用する必要はありません。
セカンドオピニオンはあくまで「判断材料の一つ」。
複数の意見を聞いた上で、最終的にどうするかを決めるのは施主であるあなた自身であることを忘れないでください。
注意点③ 担当者との関係を悪化させない
診断結果をそのままハウスメーカーの担当者に突きつけると、「私たちが一生懸命考えたプランを否定された」と感じ、関係が悪化することがあります。
スマートな伝え方の例としては、以下のような「言い回し」を使うのがおすすめです。
- 「親戚に建築関係の人がいて、少し見てもらったらこんなアドバイスをもらったんですが、検討できますか?」
- 「友人の家を見て気づいたんですが、ここをこうすることは可能ですか?」
- 「自分なりに勉強して気になったのですが…」
「ネットで診断してもらった」と正直に言うよりも、身近な例を出したり、自分の意見として相談したりする方が、担当者のプライドを傷つけずに修正を依頼しやすくなります。
間取り診断サービスのおすすめに関するQ&A
間取り診断サービスのおすすめに関するQ&Aに回答していきます。
Q1. 診断をお願いするときって、図面のほかに何を用意すればいいの?
A1. 基本的には「現在の間取り図(寸法入り)」があれば診断可能です。
ただし、より精度の高いアドバイスをもらうためには、敷地の状況がわかる「求積図」や「配置図」、周辺環境の写真、そして「家族構成や要望をまとめたメモ」も用意するのがおすすめです。
情報は多いほうが、建築士も具体的な提案がしやすくなります。
Q2. 診断してもらった結果を、そのままハウスメーカーの担当者に見せても大丈夫?
A2. トラブルを避けるため、診断結果のレポートをそのまま渡すのは避けたほうが無難です。
「別の建築士に見せた」と伝えると、担当者のプライドを傷つけたり、警戒されたりする可能性があります。
記事内の「伝え方のコツ」でも触れたように、「親戚のアドバイス」や「自分の希望」として、かみ砕いて伝えるのが円満に進めるポイントです。
Q3. 申し込んでから結果が来るまで、大体どれくらいの日数がかかる?
A3. サービスの規模によりますが、ココナラなどの簡易診断であれば「3日〜1週間程度」、設計事務所による本格的な診断や新プラン作成なら「2週間〜1ヶ月程度」が目安です。
次の打ち合わせまでに結果が欲しい場合は、納期に余裕を持って依頼するか、事前に「特急対応」が可能かを出品者に確認しましょう。
Q4. 家事動線だけじゃなくて、風水とか家相も見てほしいんだけど対応してる?
A4. 一般的な建築士による診断は「機能性」や「構造」が中心で、風水は専門外の場合が多いです。
もし風水や家相を重視したい場合は、ココナラなどで「風水鑑定士」の資格を持つ専門家を探すか、プロフィールに「家相診断可能」と明記されている建築士を選ぶようにしましょう。
Q5. 数千円で頼める安いサービスって、本当に役に立つの?安すぎて不安……。
A5. 安いサービスは「図面の赤ペン添削」や「ワンポイントアドバイス」に限定されていることが多いため、低価格で提供されています。
本格的な設計変更や構造計算は含まれませんが、「第三者の意見を聞いて安心したい」「明らかな欠陥がないか確認したい」という目的であれば、コストパフォーマンスは非常に高く、十分に役立ちます。
Q6. 提案してもらった間取りが、実際には建てられないことってあるの?
A6. はい、あり得ます。ハウスメーカーごとに「標準仕様」や「独自の工法(2×4や鉄骨など)」による制約があるためです。
診断を依頼する際は、必ず「検討中のハウスメーカー名」や「工法」を伝え、その制約の中で実現可能なアイデアを出してもらうようお願いすると、実現性が高まります。
Q7. 図面のデータがないんだけど、スマホで撮った写真でも依頼できる?
A7. はい、多くのサービス(特にココナラやLINE相談系)では、スマホで撮影した写真データで対応してくれます。
ただし、文字や寸法がぼやけていると診断ができないため、明るい場所で真上から撮影し、数字がはっきり読めるか確認してから送るようにしてください。
Q8. 診断結果を見て「なんか違うな」って思ったら、修正や質問は追加でできる?
A8. サービスによって異なります。「1回まで質問無料」や「修正は別料金」など、出品者ごとにルールが決まっています。
契約前に「修正は何回まで無料か」「診断後の質問期間はあるか」を確認しておくと安心です。
納得いくまで相談したい場合は、サポート期間が長いサービスを選びましょう。
Q9. もう契約しちゃった後なんだけど、今から診断してもらう意味ってあるかな?
A9. 「大幅な変更」は追加費用がかかるため難しいですが、コンセントの位置や扉の開き方、収納棚の高さなど、着工直前まで変更可能な「微調整」のアドバイスをもらう意味は十分にあります。
住んでからの「使いにくい」を減らす最終チェックとして活用するのも一つの方法です。
Q10. 結局、どこに頼むか迷う……。一番失敗しない選び方は?
A10. 「何に一番不安を感じているか」で決めましょう。
「予算をかけずに安心感が欲しい」ならココナラで評価が高い人、「家事動線や収納を徹底したい」なら女性建築士(みゆう間取り相談室など)、「性能や欠陥リスクを排除したい」なら総合コンサル(かえる建築事務所など)がおすすめです。
まずは無料のタウンライフなどで比較するのも良いスタートです。
Q11. 診断をお願いしてる間に、工事の予定が遅れちゃったりしない?
A11. 診断自体は1週間程度で終わりますが、そこでもし「大幅な間取り変更」をすることになった場合、ハウスメーカー側の図面修正や再見積もりに時間がかかり、全体のスケジュールが押してしまう可能性はあります。
引き渡し時期を遅らせたくない場合は、できるだけ早い段階(契約前や詳細設計の初期)に診断を依頼するのが安全です。
Q12. 「これだけはやめとけ」っていう、住んではいけない間取りってある?
A12. 風水的な観点を除けば、実用面で避けるべきなのは「家事動線が複雑で遠回りを強いられる間取り」や「採光・通風が全く考慮されていない部屋がある間取り」です。
また、流行りを詰め込みすぎて「収納が極端に少ない(または使いにくい場所にある)」ケースも後悔の原因になります。
これらは図面だけでは気づきにくいため、プロのチェックが有効です。
Q13. アプリで自分で間取りを作ってみるのってどう?おすすめはある?
A13. 自分の希望をイメージするにはとても良い方法です!「マイホームクラウド」や「Planner 5D」などの無料アプリが人気で、パズル感覚で部屋を配置できます。
ただし、アプリで作った間取りは「構造的な強度」や「法的な制限」が考慮されていないことが多いので、あくまで「希望を伝えるためのたたき台」として使い、最終的な調整は必ずプロにお任せしましょう。
Q14. 最近話題のAI(人工知能)で間取り診断ってできないの?
A14. AIによる間取り作成や簡易診断サービスも登場してきています。
瞬時にパターンを出してくれるのは魅力ですが、現時点では「その土地特有の光の入り方」や「家族ごとの細かい生活習慣」まで汲み取った提案は、やはり経験豊富な人間の建築士に分があります。
AIはアイデア出しの補助として使い、最終判断は建築士のセカンドオピニオンを仰ぐのがおすすめです。
Q15. 今みんなが採用してる、人気の間取りランキングってどんなの?
A15. 近年のトレンド上位は、行き止まりのない「回遊動線」、洗濯を1ヶ所で完結できる「ランドリールーム」、家族の衣類をまとめて収納する「ファミリークローゼット」などが非常に人気です。
これらは確かに便利ですが、敷地の広さや家族構成によっては逆に居住スペースを圧迫することもあります。
「人気だから」で採用せず、自分たちに合うかを診断時に相談してみましょう。
間取り診断サービスおすすめまとめ:「後悔しないための必要経費」で納得のいく家づくりを!
今回は、間取り診断サービスのおすすめについて解説しました。
注文住宅は、人生で最も高価な買い物の一つです。
完成してから「もっとこうすればよかった」「なんで気づかなかったんだろう」と後悔しても、簡単に買い替えることはできません。
間取り診断にかかる費用は、数千円から高くても10万円程度。
住宅価格全体から見ればわずかな金額ですが、それによって得られる「住み心地の良さ」や「失敗を防げたという安心感」は、価格以上の価値があります。
ただ、もしあなたが「今の図面の手直しだけでは満足できない」「もっと全く違う視点のアイデアが欲しい」と感じているなら、診断を受ける前に「選択肢そのものを増やす」のも一つの手です。
そこで、とくにおすすめなのが、無料で利用できる「タウンライフ家づくり」です。
スマホから要望を入力するだけで、厳選された複数のハウスメーカーや工務店から、あなただけの「オリジナル間取りプラン」と「見積もり」を一括で取り寄せることができます。
- 今のメーカー以外の「別の正解」が見つかるかもしれない
- セカンドオピニオンに見てもらうための「比較材料」が増える
- 完全無料なので、金銭的なリスクがゼロ
「今の間取りを診断してもらう」のも大切ですが、「他のプロならどう提案するか」を知ることも、視野を広げるための立派なセカンドオピニオンと言えます。
ぜひ、有料の間取り診断サービスと合わせて「タウンライフ家づくり」も賢く活用し、100%納得のいく理想のマイホームを実現させてくださいね。
間取りで後悔だらけを防ぐ方法!注文住宅の失敗例と対策を徹底解説
-

-
間取りで後悔だらけを防ぐ方法!注文住宅の失敗例と対策を徹底解説
続きを見る
洗濯導線の良い間取りとは?家事負担を減らすランドリールーム・収納・動線設計を徹底解説!
-

-
洗濯導線の良い間取りとは?家事負担を減らすランドリールーム・収納・動線設計を徹底解説!
続きを見る
注文住宅の収納計画の立て方!後悔しない間取りを実現する4つのステップと場所別アイデアを解説!
-

-
注文住宅の収納計画の立て方!後悔しない間取りを実現する4つのステップと場所別アイデアを解説!
続きを見る